中山町の歴史
令和
| 2023年 令和5年 |
12月 お達磨の桜公園に、お達磨のサクラの二世木を植樹 11月 「地域おこし協力隊」として新たに1名が着任 10月 大塚製薬株式会社と「町民の健康づくりに関する包括連携協定」を締結 9月 町公式ホームページをリニューアル 8月 「夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が開催される 7月 4年ぶりに「第30回全国かぶと虫相撲大会」を開催 5月 「チャレンジデー」に7度目の参加 4月 浸水害対策水防拠点施設が完成 3月 地域おこし協力隊1名(第二期)が退任 2月 地域おこし協力隊1名(第二期)が退任 |
|---|---|
| 2022年 令和4年 |
11月 消防車両1台を更新 9月 3年ぶりに「第13回元祖芋煮会in中山」を開催 「第1回すももウォーキング」を開催 8月 「令和4年8月豪雨災害」発生 町中心部の道路が冠水 5月 「チャレンジデー」に6度目の参加 町観光協会が制作した「芋煮会発祥の地」PR動画が、東北映像フェスティバル2022「映像コンテスト」の【地域振興コンテンツ部門】で大賞を受賞 4月 「地域おこし協力隊」として新たに1名が着任 3月 明治安田生命保険相互会社と「健康増進に関する連携協定」を締結 山形県建築士会山形支部と「災害時における被災建築物応急危険度判定業務に関する協定」を締結 2月 ひまわり温泉ゆ・ら・ら 入浴者800万人達成 1月 新型コロナウイルス感染症の流行により、延期した成人式を開催 中山町豪雪対策本部を設置 |
| 2021年 令和3年 |
11月 なかやま観光大使に春風亭昇りんさんが着任 |
| 2020年 令和2年 |
12月 「災害等における災害廃棄物処理に関する協定」を締結 |
| 2019年 令和元年 |
11月 旧柏倉家住宅重要文化財指定記念シンポジウムを開催 |
平成
| 2019年 平成31年 |
4月 柏倉家住宅保存・利活用実施計画を策定 |
|---|---|
| 2018年 平成30年 |
10月 西郷従道の玄孫の西郷真悠子氏が来町(トークショーや町民との交流を行う) |
| 2017年 平成29年 |
10月 まちづくりシンポジウム 「西郷兄弟に学ぶ中山町の未来」を開催 |
| 2016年 平成28年 |
12月 「最上川が運んだ文化と黒塀の豪農屋敷群」が「未来に伝える山形の宝」に登録 |
| 2015年 平成27年 |
12月 株式会社楽天球団と「スポーツ交流活動等に関するパートナー協定」を締結 |
| 2014年 平成26年 |
12月 大津保信町長が死去 |
| 2013年 平成25年 |
12月 役場西側庁舎(議場棟)耐震補強工事完了 |
| 2012年 平成24年 |
12月 金沢白山神社の『菓子屋図絵馬』を町文化財に指定 |
| 2011年 平成23年 |
12月 中山町の消防事務を山形市へ委託開始 |
| 2010年 平成22年 |
12月 『ひまわり娘』リニューアル。『すももスパークリングワイン』誕生 |
| 2009年 平成21年 |
12月 中山町消費生活相談窓口を設置 |
| 2008年 平成20年 |
10月 ふるさと寄附金受付スタート |
| 2007年 平成19年 |
9月 羽越水害から40年 |
| 2006年 平成18年 |
8月 ひまわり温泉ゆ・ら・ら夏祭り初開催 |
| 2005年 平成17年 |
10月 中山町行政改革大綱を策定 |
| 2004年 平成16年 |
10月 中山町誕生50周年記念式典 |
| 2003年 平成15年 |
11月 NHKラジオ公開録音「ふるさと自慢うた自慢」収録 |
| 2002年 平成14年 |
12月 あおば橋と県道長岡中山線が開通 |
| 2001年 平成13年 |
12月 中山町行政イントラネット始動 |
| 2000年 平成12年 |
1月 町制施行45周年記念町づくり講演会講師に北野大氏を招き超満員 |
| 1999年 平成11年 |
10月 中山町誕生45周年記念式典が開催される |
| 1998年 平成10年 |
12月 特別養護老人ホーム中山ひまわり荘完成 |
| 1997年 平成9年 |
11月 町民テニスコートが照明灯と人工芝でリニューアル |
| 1996年 平成8年 |
10月 粗大ごみ(PDFファイル:317.7KB)が有料化 |
| 1995年 平成7年 |
12月 ひまわり温泉ゆ・ら・ら周辺の愛称が『ひまわり元気のさと』に決定 町民休養交流センターの第2期工事として、町民待望の体育館が完成し、オープンを記念して11月5日にNHKのど自慢が開催された。 8月 東新堀橋完成 |
| 1994年 平成6年 |
11月 文部省地域指定道徳研究発表会が開かれる |
| 1993年 平成5年 |
12月25日 ひまわり温泉ゆ・ら・らがオープン 町民休養交流センターの第1期工事として建設。 10月1日 柏倉亮吉氏・今野半次郎氏が初めての名誉町民になる 8月5日 町民休養交流センターの愛称が「ゆ・ら・ら」と決定 町民交流センター工事着工される |
| 1992年 平成4年 |
歩道除雪用小型ロータリー車を導入 |
| 1991年 平成3年 |
上町コミュニティセンター完成 ふるさと創生1億円を活用し、温泉を掘削していた |
| 1990年 平成2年 |
中山町流域関連公共下水道の本格着工が始まる |
| 1989年 平成元年 |
都市計画道路中山公園線竣工 |
昭和
| 1988年 昭和63年 |
ミニバスケット女子チームが全国大会に男子チームが東北大会に出場 |
|---|---|
| 1987年 昭和62年 |
落合構造改善センター完成 |
| 1986年 昭和61年 |
2月1日 住民課窓口業務が手作業から電算処理に移行 |
| 1985年 昭和60年 |
10月1日 開かれた町政を推進しようと情報公開制度がスタート |
| 1984年 昭和59年 |
ながきき幼稚園が開園 |
| 1983年 昭和58年 |
1月 NHK朝の連続テレビ小説「おしん」のロケが岩谷地区で行われる |
| 1982年 昭和57年 |
9月19日 第1回なかやまアユまつりが最上川河川敷で開催。 |
| 1981年 昭和56年 |
桜町に県営長崎アパートできる |
| 1980年 昭和55年 |
国鉄羽前長崎駅の貨物取り扱いが廃止される |
| 1979年 昭和54年 |
国道112号中山バイパスが開通 3月2日 長崎小学校の新校舎が完成 |
| 1978年 昭和53年 |
町の民謡「最上船頭唄」「中山音頭」がレコード化される |
| 1977年 昭和52年 |
県営ほ場整備事業の実施調印取りまとめ開始(53年着工) |
| 1976年 昭和51年 |
東北横断自動車道酒田線山形・寒河江間のルー卜が発表 |
| 1975年 昭和50年 |
スポーツ分団対抗の「社会体育大会」がスタート |
| 1974年 昭和49年 |
4月10日 町立ひばり保育園開所(定員90、中央公民館南側)。 「お知らせ版」が発行開始 |
| 1973年 昭和48年 |
中山町商工センターが完成 4月 中山町総合開発計画が策定される 成人式が初めて夏に行われる |
| 1972年 昭和47年 |
中学校サッカ一部県大会で初優勝 |
| 1971年 昭和46年 |
農業振興地域に指定される |
| 1970年 昭和45年 |
普通電話がダイヤル式自動化になる 学校給食共同調理場が完成し、業務を開始 |
| 1969年 昭和44年 |
豊田小学校プールが完成 新都市計画法が施行され、中山町が山形広域都市計画区域に指定される |
| 1968年 昭和43年 |
11月21日 中山中学校新校舎に移り、体育館建設工事に着手。 9月 第1回町民レクリェーション大会が開催される。(昭和45年まで3回開催) |
| 1967年 昭和42年 |
豊田地区に集団赤痢発生 第3代中山町長に石山甚平氏が就任 |
| 1966年 昭和41年 |
4月 役場庁舎改築工事が完成 国土調査法に基づく「地籍調査」が開始される |
| 1965年 昭和40年 |
4月7日 長崎中学校・豊田両中学校を統合し、中山中学校となる。 石子沢川下流改修工事完成 |
| 1964年 昭和39年 |
8月 中山町盆踊り花火大会開催(北小路自動車練習場(コメリ付近) 昭和42年まで4回開催) |
| 1963年 昭和38年 |
町ではじめての舗装工事が実施される。 |
| 1962年 昭和37年 |
長崎小学校創立80周年となる。 |
|
1961年 昭和36年 |
10月31日 町営斎場が完成。 4月10日 町立桜保育園開所(定員60、旧役場豊田支所(現豊田小北側)を改築)。 |
| 1960年 昭和35年 |
12月 豊田小学校が学校衛生統計で文部大臣表彰を受ける |
| 1959年 昭和34年 |
6月 長崎~天童間のバス開通。 |
| 1958年 昭和33年 |
10月 岡経由山形行きバスが開通。 |
| 1957年 昭和32年 |
11月 最上川鉄道橋より上流634メートルが築堤。 |
| 1956年 昭和31年 |
12月 金沢簡易水道が完成。 長崎地区上水道工事の起工式。 |
| 1955年 昭和30年 |
8月26日 町章が制定される。 中山町体育協会が結成される。 |
| 1954年 昭和29年 |
12月 中山町商工会が発足。 初代町長に高橋幸男氏就任。 |
| 1953年 昭和28年 | テレビ(白黒)放送始まる。 |
| 1951年 昭和26年 | 4月 町立若草保育園開所(定員90、柳町天性寺敷地内)。金沢駅できる。 |
| 1947年 昭和22年 | 「中学校」創立、PTAできる、赤痢流行る |
| 1945年 昭和20年 | 「終戦」戦没者 軍人376・軍属3 計379 |
| 1944年 昭和19年 | 農業会(今の農業協働組合)できる |
| 1938年 昭和13年 | 村山豊田郵便局できる |
| 1936年 昭和11年 |
土橋に農業しゅうよう道場たつ。 |
| 1934年 昭和9年 | 大暴風と凶作 |
| 1933年 昭和8年 | 最上川の木の橋を鉄筋コンクリートにかえる |
大正
| 1912年 大正1年 | 日本がオリンピックに初めて参加 |
|---|---|
| 1913年 大正2年 | 大洪水浸水822戸 |
| 1914年 大正3年 | 乗り合い自動車走る、第一次世界大戦おこる。 |
| 1921年 大正10年 | 「左沢線」開通。鉄道が敷かれ長崎駅ができる。 |
| 1923年 大正12年 | 関東大地震。 |
| 1924年 大正13年 | 消防自動車を備える。 |
| 1925年 大正14年 |
長崎小学校前の木の橋を鉄きんコンクリートにつくりかえる、ラジオ放送が始まる。 |
明治時代
しばしば行政区の改正が行われ、明治22年(1889年)町村制施行により、長崎、達磨寺、向新田の3か村が合併して最上村になり、岡、土橋、柳沢、金沢、小塩の5ヶ村は豊田村となった。
その後、明治30年(1897年)に最上村は長崎町と改称された。
| 1872年 明治5年 | 長崎郵便局できる。 |
|---|---|
| 1874年 明治7年 | 人力車走る。 |
| 1876年 明治9年 | 山形県に編入。 |
| 1877年 明治10年 | 長崎に村役場おかれる、乗り合い馬車走る。 |
| 1878年 明治11年 | 東村山郡に編入。 |
| 1879年 明治12年 | コレラはやる。 |
| 1882年 明治15年 | 「長崎学校」開業式 農商務卿西郷従道臨席。 |
| 1884年 明治17年 | 岡村役場がおかれる。 |
| 1887年 明治20年 | さくらんぼ・りんご・ぶどうの苗植える。 |
| 1888年 明治21年 | 最上堰できる。最上堰水利事業起工12月通水。 |
| 1889年 明治22年 | 長崎村を最上村とかえる。「町村制施行」向新田村、達磨寺村、長崎村合併し最上村、金沢村、柳沢村、土橋村、岡村、小塩村合併し豊田村 |
| 1894年 明治27年 | 日清戦争おこる。 |
| 1895年 明治28年 | 最上川に木の橋できる |
| 1897年 明治30年 | 最上村を「長崎町」と改める。長崎郵便電信局できる。 |
| 1899年 明治31年 | 長崎銀行できる |
| 1900年 明治32年 | 電灯がはじめてつく |
| 1902年 明治35年 | 動力の米つき会社できる |
| 1903年 明治36年 | 豊田小学校校舎落成(土橋) |
| 1904年 明治37年 | 自転車走る、日露戦争おこる |
| 1905年 明治38年 | 織物工場できる |
| 1907年 明治40年 | 大洪水 |
| 1909年 明治42年 | 日照りがつづき、被害出る |
| 1911年 明治44年 | 電話が通じるようになる |
江戸時代
元和8年(1622年)山形の最上氏没落とともに中山氏も滅び、長崎楯は廃止された。その後、長崎領は山形鳥居忠政の支配下に属し時代とともにある時は山形領、ある時は幕領になるなど幾変遷を経て幕末に至った。その間、地区によって異なる支配を受けたこともある。
| 1622年 元和8年 | 最上家改易となり中山氏去る。(こののち村々は山形藩、幕府、大名飛地領などと複雑な行政のもとで明治に至る。) |
|---|---|
| 1672年 寛文12年 | 河村瑞軒が江戸に至る「西廻航路」実現 |
| 1694年 元禄7年 | 「置賜」と「長崎」間の最上川筋の工事が完成し長崎舟場が栄えていく。 |
| 1731年 享保16年 | 岡の「柏倉九左工門」が山形、堀田領の「大庄屋」を長くつとめ村々のためにはたらく。 |
| 1741年 寛保1年 | 長崎村名主「黒沼源右工門」の働きにより「柳沼」が完成し長くかんがい用水として役に立つ。 |
| 1757年 宝暦7年 | 「最上川大洪水」平水より高きこと三丈余(9メートル) |
| 1768年 明和5年 | 光秀院に「大日如来」(湯殿山本尊)座像たつ。郷土の街道は三山参りでにぎわう。 |
| 1815年 文化12年 | 春、長崎舟場より送った城米3.618俵10ケ村分。 |
| 1830年 文政13年 |
長崎村百姓代弥右工門の「最上流紅花の作り方」全国に紹介される。 |
| 1833年 天保4年 | 奥羽大凶作、中山地区四村より義援金570両 |
| 1868年 慶応4年 (明治1年) |
戊辰の役「落合の戦」山形藩士4名戦死。 |
室町時代
継信の孫宗朝は長崎楯の整備につとめ、楯を中心に城下町づくりを進めるいっぽう、寛正5年(1464年)には谷木沢(現在の柳沢)に山楯を築いた。
中山氏は領地が12ヶ村8千石で、舟運の便を図るなど、戦国時代には、村山地方の豪族として確固たる地位を占めていた。
| 1445年 文安2年 | 3代「宗朝」のとき「長崎楯」と「堀」ができる。これから中山氏代々によって町づくりがなされる。 |
|---|---|
| 1464年 寛正5年 | 4代「朝勝」谷木沢に「山楯」をつくる。 |
| 1503年 文亀3年 | 「直正」の娘「山野辺直広」に嫁ぐ。「立道」できる。 |
| 1526年 大永6年 | 谷木沢楯をなくす。(開館以来61年) |
| 1583年 天正11年 | 8代玄蕃頭「朝政」没す。楯に居ること約60年。玄蕃さまと慕われる。玄蕃壇にまつる。 |
| 1584年 天正12年 | 9代主王蕃頭「朝正(光直同人)」山形城主「最上義光」の家臣となる。石高七干石 領地12カ村 |
| 1587年 天正15年 | 最上義光庄内を攻め朝正を大浦(大山〉城の城代とする。 |
南北朝時代
| 1,333~1,391年 | 中山氏は次第に勢力を得、継信の時に初めて中山町に入り、長崎楯を作り始めました。 元中元年(1384年)のことです。 楯の大イチョウは樹齢500年余と推定され、町の歴史を秘めてそびえたつ姿は、中山町の象徴と言えるでしょう。 |
|---|
鎌倉時代
承久の変(1219年)の時、後鳥羽上皇で朝廷方に味方して敗れ鎌倉方の重臣大江親広とともにこの地方に落ちのびた中山忠義(中山氏の始祖)は、わが町一帯の開発につとめた。
至徳元年(1384年)に長崎に楯(城)が築かれ、7代目中山継信が長崎楯主としてはじめて中山氏の基礎を固めた。
| 1221年 承久3年 | 承久の変後長崎城主中山氏の遠祖中山忠義、大江氏とともに寒河江荘にのがれ伏熊(大江町)におちつき、代々住む。 |
|---|---|
| 1384年 至徳元年 | 「中山左衛門継信」初めて長崎村に楯をつくる。 |
奈良時代
| 710~783年 | 和銅5年(712年)出羽国が誕生し、中山町は出羽国最上郡に属していました。 |
|---|
飛鳥時代
| 592~709年 | 三軒屋から発見された土師器(はじき)は7世紀頃と言われています。 つぼ、わん、さら、こしき、たかつきなどと数多く、形がいろいろで珍しく、柏倉先生は「三軒屋式土師器」と名付けました。 この頃すでに最上川河畔で稲作が行われていたのです。 今からおよそ1,000年前には山形盆地に条里制がしかれ、口分田が配給されたという事実が柏倉先生の調査で明らかにされました。 中山町には柳沢に三条目、土橋に一の坪という地名が今も残っています。 |
|---|
大和時代
| 366~591年 | 中山町は5世紀頃から平地部が開拓され、達磨寺須川淵から出土した土師器(はじき)がそれを証拠づけています。 土師器は農耕文化の発達に伴い、数多く使用されるようになりました。 |
|---|
弥生式文化時代
| 紀元前300年頃~ | 金沢の庚申山に弥生式土器らしいものが発見され、稲作文化の始まりが考えられます。今から2,000年前のことです。 |
|---|
縄文式文化時代 ~人が住みはじめる~
|
紀元前6、7千年ごろ およそ3,000~5,500年前 |
主な遺跡 松岡山遺跡(小塩)、影浦遺跡(岡)、御嶽神社遺跡(柳沢) 小塩の松岡山からおよそ5,500年前、岡の影浦、柳沢の御嶽神社遺跡からは4,500年前の石器や土器が出土し、当時の山形大学教授の柏倉先生によって確認されました。 |
|---|
中山町の歴代町長
| 代 | 名前 | 在職期間 |
|---|---|---|
| 9代 | 佐藤俊晴 | 平成27年1月25日 ~ |
| 8代 | 大津保信 | 平成20年10月26日 ~ 平成26年12月3日 |
| 7代 | 宇津井弘治 | 平成11年4月30日 ~ 平成20年10月25日 |
| 6代 | 縄野裕史 | 昭和62年4月30日 ~ 平成11年4月29日 |
| 5代 | 石川金男 | 昭和54年4月30日 ~ 昭和62年4月29日 |
| 4代 | 若林幸三郎 | 昭和46年4月30日 ~ 昭和54年4月29日 |
| 3代 | 石山甚平 | 昭和42年4月30日 ~ 昭和46年4月29日 |
| 2代 | 服部久 | 昭和30年5月22日 ~ 昭和42年4月29日 |
| 初代 | 高橋幸男 | 昭和29年10月31日 ~ 昭和30年4月29日 |
中山町の歴代議長
| 代 | 名前 | 在職期間 |
|---|---|---|
| 26代 | 鎌上徹 | 令和3年1月12日 ~ |
| 25代 | 堀川政美 | 令和元年10月1日 ~ 令和2年12月11日 |
| 24代 | 斎藤眞一 | 平成31年3月1日 ~ 令和元年9月30日 |
| 23代 | 小関敏明 | 平成29年10月2日 ~ 平成31年2月28日 |
| 22代 | 斎藤眞一 | 平成27年10月1日 ~ 平成29年10月2日 |
| 21代 | 須貝勝司 | 平成27年1月30日 ~ 平成27年9月30日 |
| 20代 | 鈴木徹雄 | 平成25年10月1日 ~ 平成27年1月16日 |
| 19代 | 須貝勝司 | 平成23年10月1日 ~ 平成25年10月1日 |
| 18代 | 小関敏明 | 平成21年10月1日 ~ 平成23年9月30日 |
| 17代 | 佐東貞美 | 平成19年10月1日 ~ 平成21年10月1日 |
| 16代 | 工藤芳夫 | 平成15年10月1日 ~ 平成19年9月30日 |
| 15代 | 渡邉雅弘 | 平成11年10月1日 ~ 平成15年9月30日 |
| 14代 | 佐東左一 | 平成9年5月23日 ~ 平成11年9月30日 |
| 13代 | 大関吉昭 | 平成3年10月1日 ~ 平成9年5月23日 |
| 12代 | 秋葉駿平 | 昭和58年10月1日 ~ 平成3年9月30日 |
| 11代 | 高橋幸一郎 | 昭和54年10月1日 ~ 昭和58年9月30日 |
| 10代 | 高橋啓 | 昭和54年3月16日 ~ 昭和54年9月30日 |
| 9代 | 森谷喜四郎 | 昭和50年10月1日 ~ 昭和54年3月16日 |
| 8代 | 大山義雄 | 昭和50年6月9日 ~ 昭和50年9月30日 |
| 7代 | 西塔一栄 | 昭和48年9月27日 ~ 昭和50年3月31日 |
| 6代 | 原田与惣右衛門 | 昭和46年10月1日 ~ 昭和48年9月27日 |
| 5代 | 秋葉喜久弥 | 昭和37年10月19日 ~ 昭和46年9月30日 |
| 4代 | 柏倉喜右ェ門 | 昭和34年10月6日 ~ 昭和37年10月19日 |
| 3代 | 佐東彦右衛門 | 昭和33年8月20日 ~ 昭和34年9月30日 |
| 2代 | 井上忠一 | 昭和30年10月1日 ~ 昭和33年7月18日 |
| 初代 | 松田敏雄 | 昭和29年10月1日 ~ 昭和30年9月30日 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(広報・統計・情報担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2223
ファックス:023-662-5176
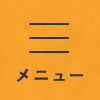
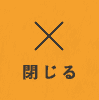

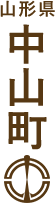




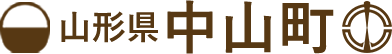
更新日:2024年04月01日