ひと・夢・まち 町長コラム(令和6年)
(広報なかやまより)
東京で「いも煮ケーション」(令和6年12月号)
先月の一か月間、東京千代田区の「ちよだグルメショップ+A」にて、中山町フェアが開催されました。このフェアは、町をPRすることが目的で、特産品である米・フルーツ(ラ・フランス、りんご)・北前いも煮などを販売すると、予想以上の反響があり、陳列された品々は当日には無くなってしまうという大盛況ぶりだったようです。本場の産物への興味や安心感とともに、新鮮な香りに引き寄せられる食に対する欲求は人間の本能なのだと実感しました。
月末には同施設内の「結ぶ食房 しまゆし」にて、中山町A級グルメナイト「いもにでナイト」を 開催。5000円という参加費にもかかわらず定員 20名の方々が来場し、楽しんでいただきました。開会の挨拶で「芋煮会発祥の地」であることをPR 、すももワインで乾杯、北前いも煮と中山町の食材を使った料理を楽しみ、最上川舟運で栄えてきた町の歴史や情景など、様々な話題で盛り上がりました。中山町のことを全く知らなかった参加者も、いも煮を食しながら話が弾み、中山町に興味を持っていただき、まさに【 いも煮ケーション 】の真髄を感じた 時間でした。
町民の皆様におかれましては、地元の美味しい食べ物などを家族で囲みながら一年
を振り返り、輝かしい一年を迎えられますことを願っています。
JR地方路線の赤字、路線廃止と地方創生に思うこと(令和6年11月号)
先月末の新聞一面に「JR地方路線赤字」との記事が載っていました。県内5区間でも赤字幅拡大とあり、左沢線(寒河江ー左沢間)もその一つに挙げられていました。左沢線は、大正10年に開通し、以来通勤・通学を主に町民の生活を支え、地域経済の活性化に直結してきました。JR地方路線赤字と路線廃止は、地方創生にとって非常に重要な課題です。
昭和62年4月の分割民営化以降、JR各社は効率的な運営を目指してきましたが、時代の変遷と共にJRの利用客が減少し厳しい運営状況にあります。さらに、度重なる災害により復旧もままならない米坂線の現状もあります。一考として、鉄道の上下分離方式(運営と施設の管理を分ける)の検討も含め、地域ごとの状況を考慮し連携を強化しながら、持続可能な地域交通ネットワークを構築することが地方にとって重要と思うのです。
私も高校時代に毎日お世話になった左沢線、現在はSuicaも使えるようになり出張時や私用でときどき利用しています。車窓からの豊かな景色を眺めながら、存続と利用拡大について、できる限りのことを思案すべきだと思っています。
待ちに待った国道112号・山形中山バイパスが実現化に (令和6年10月号)
去る9月29日、国道112号・山形中山道路の起工式が、出発地点である達磨寺地内(弁財天南側)にて挙行されました。
30年におよぶ地域の念願であったこの工事の着手は、単なるインフラ整備にとどまらず、中山町にとっての新しい希望の象徴であります。この日を迎えることができましたのも、地域の皆様の長年のご努力とご協力の賜物でございます。ともに喜び、感謝申し上げたいと思います。
この山形中山道路が完成することによって、地域の交通利便性が大きく向上し、経済活動の活性化が期待されます。人々の暮らしの生活圏が広がり、訪れる方々にとっても魅力的な地域となる希望の幹線道路であります。さらに、災害時の第一次緊急輸送道路として、広域避難や救急医療活動における基幹道路としての役割が期待されています。
中山町の未来を切り開く一翼を担うこの道路が、夢をはぐくむ幹線道路となることを心より願っています。今後とも、町民の皆様とともにこのプロジェクトを見守り、協力し合いながら、素晴らしい未来を築いていくため努力してまいります。
日本から来たヒーロー・中村哲 ~医師・中村哲ドキュメント映画を鑑賞して~(令和6年9月号)
2019年12月、人道支援を続けていたアフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。現地での35年にわたる活動の中で、医療に留まらず井戸掘り、用水路建設と、目の前の命に救いの手を差し伸べてきた。2010年に完成させた用水路は今も65万人の生活を支えている(良心の実弾〜医師・中村哲が遺したもの〜より)。
彼の進めてきた用水路建設事業は、先進国である進歩的な技術に頼ることはなく、地元住民で造り上げることにこだわり、その完成した施設は、人をつくり地域をつるという信念があったようである。さらに、地域住民が自分事として自然と対峙し自立することを伝えたかったように思える。
生前、作家・澤地久枝さんとの対談で、澤地さんが後継者について問いかけると、「後継者はいない。人の名前は忘れられる。しかし、そのものは残っていく。自分たちの生活や生命に直結するものであれば、保全されるだろうと思います」と答えたと言う。中村氏の息子さんが、追悼式の中で、父の言葉で一番覚えているのは、「口で立派なことばかり言わんで行動で示せ」だったと語った。重く心に刺さる言葉である。
中村哲、未来に語り繋いでいかなければならない人物の一人であると感じている。
オリンピックシンボルは団結のしるし(令和6年8月号)
1914年、クーベルタンによって考案されたのがオリンピックシンボルです。
5つの輪は五大陸を表しており、世中の人々がオリンピックを通して友情を育み、協力しあって結ばれることを表現しています。 そしてその色は、青、黄、黒、緑、赤の5色に、旗の地の白を加えた6色。これらの色で世界の国々の国旗がほとんど描けることから、「世界は一つ」との意味が込められています。
パラリンピックシンボルは「スリーアギトス」と呼ばれ、赤、青、緑の3色の曲線で描かれています。「アギト」はラテン語で「私は動く」を意味し、困難なことがあっても諦めずに、限界に挑戦し続けるパラリンピアンを表現しています。
クーベルタンは、平和のための近代五輪の提唱と同時に、スポーツと教育を結び付けた第一人者でもありました。スポーツが健全な体を作り、自分自身の限界に挑戦し、一方で他者を尊重し、フェアプレーを大切にする豊かな心を育てると…。
彼のゆかりの地でもあり、歴史と伝統が息づく街で行われる五輪だからこそ、競技という枠組みの中で国際的な交流が行われ、世界に平和を訴える舞台になってほしいと切に思うのです。
「プレーヤーズセンタード」でつくる未来でつくる未来・・・(令和6年7月号)
先日、多数のスポ少関係者含む参加者のもと日本体育大学の伊藤教授による「プレーヤーズセンタード・コーチングのススメ」と題しての講演会が開催されました。これからの子どもたちへのコーチングの在り方をはじめ、環境づくりについての話を伺い、今後のまちづくりについても共通する課題であると感じたところです。現在も多くの指導者が思っている「プレーヤーズファースト」という言葉についての話の中で、実はこの言葉の次には「ウイニングセカンド」という言葉が続いていたのだが、いつしかそれが置き去りにされ「プレーヤーこそ一番」が独り歩きしてしまった現実があるとのことでした。
プレーヤー本人が勝利することは素晴らしいことではあるが、負けてしまうことが悪いことのような考え方ではなく、勝利できなかった原因を責任転嫁しないで、関係者みんなが関わり続けるという考え方「プレーヤーズセンタード:プレーヤーを人間的により成長させるという概念」を共有すべきであると感じたところです。少子高齢化の進んでいる時代、地域の住民や利用者が中心となって自らの意見やニーズを主体的に表現し、地域の魅力や資源を活用しながら共同でまちづくりをすることが未来につながっていくと感じるのです。
農家社会と脳化社会~幸福な社会とは~(令和6年6月号)
「農家社会」とは、農業を主体とした社会で、農業生産や農業の技術・発展が経済活動の基盤となる社会を指します。特徴としては、共同体意識や伝統的な価値や風土が根付いており、自給自足の生活や地域コミュニティの強固さなどが挙げられます。
一方、「脳化社会」とは、情報や知識が価値を持ち、情報処理能力や知識の獲得が重要な要素となる社会のことを指します。特徴としては、情報化やグローバル化が進み、個人主義や競争社会が浸透しており、多様性や自己表現の自由化が重視されることなどが挙げられます。
先日、新聞のコラムに「活力ある幸福な社会へ」というテーマで、解剖学者養老孟司氏のコメントが掲載されていました。その中で養老氏は、頭で考えた通りに物事を進めようとする「脳化社会」を嘆き、一極集中している都会での暮らしを疑問視しています。そして、地域ごとに食糧やエネルギーを自給自足して暮らすのが望ましい姿であると提唱しています。また、天災の備えとして、都会に住む人は地方にセカンドハウスを用意したほうが良いのではとの提案もされていました。
気候変動が様々な影響を及ぼし、南海トラフや首都直下型といった大地震も予想される昨今、同音異義語の「のうか社会」について考えながら、現代の私達はどう生きるべきかと思案しながら、地方に住む私達の力・役割はますます重要になると思うのです。
なかやま温故知新~伝えられて伝えていく~(令和6年5月号)
表題は中山町誕生70周年を迎えた今年度の取り組みにおけるスローガンです。過去の歴史や伝統を大切にしつつ、新たな価値やアイデアを生み出していく姿勢を表しています。
中山町が70周年の歴史を持つことに敬意を表し、先輩方の知恵や体験を大切にし、それらを生かしながら新しい時代に適応していく「温故知新」は、地域の発展や継続にとても重要なことです。そして、その歴史や文化、価値観を「~伝えられて伝えていく~」ことが、私たちの責任でもあります。過去から学び、それを次世代に引き継ぎ、未来へと繋いでいくことが、中山町のアイデンティティや絆を強化し、地域社会全体の発展に貢献することができると思うのです。
小塩・達磨寺地区の田植え踊り、土橋獅子踊りなどの伝統芸能は、地域で絶やさず継承され、地域の歴史と未来を結びつける優れた精神を表現しています。その他にも町内には優れた素晴らしい伝統が沢山あります。ひょっとしたら、皆さんの地域にもまだ隠れた重要な歴史があるかもしれません。それを掘り起こしていただけたら幸いです。
中山町の大切な伝統「芋煮会」。先月発表した「未来の芋煮レシピコンテスト」は、古いものを温ね新しいものを創造し、明るい町を創りあげていこうという企画です。ぜひ皆さんも一案考えていただき一緒に未来の中山町をつくっていきましょう。
芋煮会は未来をつくる!!(令和6年4月号)
さかのぼること330年前、中山町には最上川舟運で栄えた長崎湊があり、舟運に携わる船頭や商人たちでとても賑わっていました。荷揚げや荷待ちの逗留の間、時間つぶしに棒鱈と里芋を煮ていろいろな話をしながら食べていたそうです。いわゆる文化交流であり、それが芋煮会の始まりと言われています。秋の風物詩として「芋煮会」の知名度も全国的に広がり、山形県を代表する観光資源となったのです。昨年は、「芋煮会発祥の地」と「北前いも煮」の商標登録もできて、ますます芋煮会の元祖としての地位も確立してきているのではと思っているところです。
今年は中山町誕生70周年を迎えます。この様な時代の流れの中、芋煮会発祥の地として記念日制定を申請したところ、日本記念日協会より認定され、「10月2日を『芋煮会の日』として記念日登録」が決定しました。300年以上も引き継がれてきた「芋煮会」は、姿は変わってきたものの、地域の人々が集まり、協力して行う行事であり、地域の結束力や協力関係を深める機会となりうるものと思っています。芋煮会を通じて地域の伝統や文化を守り、次世代に受け継いでいくことで、わが町のアイデンティティは育っていくものと信じています。
小学生から80歳代まで・・和気あいあいと(令和6年3月号)
先月、総合スポーツクラブ主催の「町民エアバレー大会」が4年ぶりに開催された。この競技は、ビニールボール(ビーチボール)を使いバドミントンコート上で行うバレーボールのようなものである。ボールは柔らかく軽いため、年齢を問わず老若男女誰でもプレーを楽しめるのが、このスポーツの特徴であり魅力である。
今大会にも、一般チームのほか、ファミリーチームおよびシニアチームと多世代にわたる参加者が集い、真剣なプレーの中にも、多くの掛け声や笑いがあり、会場は大いに盛り上がった。80歳代を含むシニアの方々は、毎週体育館で練習しているとのこと。どうりでゲームの組み立てがなかなか上手い。無駄な動きはせず、無理に攻めようとせず、気ままに飛んでくるボールを受け止め、素直に相手コートに返す。なかなか思い通りにいかないボールとの対話は大変なはずなのに、年齢を感じさせないプレーにはただただ感心させられ、自分はまだまだだと思い知らされるのである。
人生の大先輩方の包容力のあるプレーがある限り、この町は大丈夫と感じた一日でした。来年、また会いましょう!
健全な精神は、健全な肉体に宿る(令和6年2月号)
タイトルの言葉は、古代ローマの詩人:ユウェナリスの名言です。ユウェナリスは弁護士という職業上、目を覆いたくなるような事件に多く触れており、そうした悲しい現実を嘆き憂い、現実的には、身体が健康な人が皆、精神も健康なのか?・・・異を唱えずにはいられないような事件がいろいろ起き、「健やかな身体に健やかな魂が願われるべきである」という「戒め」をこめた言葉だったようです。
その名言が時の流れとともに解釈も変わり「体が健康なら精神も健康」と使われるようになってきました。今の社会情勢を鑑みると、必ずしもそうとは言えない時代のようです。この名言の本来の意味を正しく理解し、美しい心を持てる健幸な生き方をしていかなければならないと思うのです。
今年中山町は誕生70周年を迎えます。
「なかやま温故知新~伝えられて・伝えていく~」、町の伝統や魅力を再認識する一年とし、心身ともに健康に努め、大きな一歩を踏み出していきましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
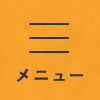
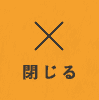

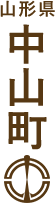




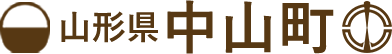
更新日:2024年12月15日