ひと・夢・まち 町長コラム(令和2年)
(広報なかやまより)
「学に志す者」大きな愛情を持っていますか?(令和2年12月号) 西郷どんの教えその23
学問を志す者は、その理想を宏大にしなければならない。しかし唯このことだけに固まってしまうと、身を修めることがおろそかになってしまう。常に自分の我に克つように修養することが大事である。学問の理想を大きく持つと同時に、自分に克つということを実践することが必要である。そして他人を自分の心の中に十分受け入れる包容力がなければならない。逆に他人の包容力に甘えるようであってはならない。
ただ、自分は正しいと思っていても、ある方向にだけ偏ってしまうことも多々あり危険である、とも心配している。
温故知新・・・故きを温ねて新しきを知る・・・多くの事象を知り学び、これからの時代のことを考えていかなければならない。今年受けた経験と教訓を、無駄にはできない。
「己れに克つ」自分に勝つ。準備はできていますか?(令和2年11月号) 西郷どんの教えその22
自分に勝つことに関してだが、普段はあまり意識せず過ごし、いざという時だけ自分に勝つぞ、と思ってもなかなかうまくいかないものだ。常日頃から、自分に勝つ心を持ってこそ、いざ事が起こった時に自分に打ち勝つことができるものだ。
「身を修めるための克己(自分の感情・欲望・邪念などにうちかつこと)は、当然己次第ということになるが、苦しい時の我慢の仕方のようにも思われるが、苦しくなった時に適当に対処することも一方法ではあるが、それではなかなか防ぎきれなくなるので、そうでなく何時どんなことがあっても、決して負けないという信念をもって日ごろ鍛えておる力に信をもって乗り切ることが最善のこと」であるという西郷さんの教えである。
7月の豪雨災害を振り返り、日々の心構えの大切さが身に染みる。
なぜ決めたことを最後までやることが難しいのでしょうか?(令和2年10月号) 西郷どんの教えその21
勉学に一生懸命取り組むということは、他人への感謝と人を愛することを目的とし、自分に勝つということをいつも考えて行動できるかどうかである。自分に勝つことの本当の目的は、論語の中で孔子が言っている「意なし、必なし、固なし、我なし」ということであり、つまり「自分さえよければという考えを持たない態度、自分さえよければという心を満たすためなら何でもやっていいというわがままな態度、他人からの忠告に一切耳を傾けようとしない態度、他人を思いやろうとしない態度」ということである。私たち人間は、自分に勝つことによって成功し、自分に負けることによって失敗する。何かを始めようとするとき、その7割から8割はたいていうまくいくが、残りの2割、3割を成し遂げる人は少ない。その原因は、はじめはヤル気も十分うまくいくことを真剣に考え頑張るが、ちょっとうまくいき他人から褒められたりすることが多くなると、自分に甘える気持ちが出てきて、最初に決めた心が揺れてくる。ここに失敗の落とし穴がある。人が見ていない時も自分に負けない心を持つことが大切である。新型コロナウイルス感染症に打ち克つ生活、各々が考えていかなければならないのです。
「途中でうまくいかなくなるのは、つい自分に甘えてしまうからである。」
「ついつい」という気持ちが、少なからず感染をくい止めることができない原因であるのでは・・・・と思える日々である。
~新型コロナ感染~大雨災害~そして絆:「中山中祭・体育祭 観覧日記」(令和2年9月号) 番外編vol.01
8月29日、中山中学校のグラウンドで第1回中山中祭・体育祭が開催されました。いろいろな行事が中止・延期されている中での開催ではありましたが、生徒会および先生方の万全なるガイドライン策定のもとの実施であると察しながら観覧させていただきました。1・2・3年生各学年のクラス対抗戦から始まります。各学年がテーマを設定しての団体リレー方式の競争です。学校全体の大きなテーマは「防災」。土のう作り、心臓マッサージ、手作り担架搬送等々、災害救助・避難準備には必要不可欠の活動が、生徒たちのたすきリレーによって表現され、チームの団結でタイムを競います。これはもはや体育祭を超えて町民を救うための防災訓練を見ているようでした。勝敗はあるものの、最後までやり遂げた生徒全員の姿に誇らしさが感じられました。皆さんご存知の通り、わが町はベッドタウンであり、昼間は子どもと高齢者が多く、お父さんお母さんは町外で働いている方が多いです。7月末の大雨災害の時も中学校の避難所設営・運営に中山中の生徒たちが協力してくれました。2年前から防災について学校全体で学びを深め、現実の災害時に対応していただき大変感謝しています。
中山町の明るい未来を感じることができた中山中祭・体育祭でした。これからも「絆」というキーワードを胸に抱き、新しい社会に飛び出していただきたいです。
なぜ必要なのか。なぜ大切なのか。話せますか?(令和2年8月号) 西郷どんの教えその20
「その人に非ざれば行われ難し」が原文であるが、どんなに新制度や方法を議論しても、それに当たる人物がいなければ運用も実行もできない。適任者があって初めて実行できるものであるから、人こそが第一の宝である。己れ自分自身がそういう人間になる心がけが肝要なことである。
「GoTo トラベルキャンペーン」が始まって初めての連休を迎えていますが(7月24日現在)、町民の皆さんはどのような生活を送っているのだろうか? 京都の嵐山では約
26%増加しているようだが、東京都内は4割~6割減っているようだ。コロナ感染者が多い都市は東京の比ではないが軒並み減少傾向にある。良いことなのか悪いことなのか賛否両論が飛び交う中、「新しい生活様式」は誰が目指すべき姿なのか? 都市圏のコロナ感染リスク、コントロールできていると思うか?のアンケートに対して、95%が思わないという結果である。確かに!
しかし、これは誰かにコントロールしてもらうことではなく、自分は何をすべきかという強い信念が重要なのである。
そしてこの事は皆わかっていることなのだと信じたいのである。うつらない事、うつさない事。手洗い、うがい、人前ではマスク。「知っているという事と、なぜ必要かを話せることは違う」のです。
みんなで一緒に安全安心の輪を広げていきましょう。その一人になりましょう。
人の意見を聞くことがありますか?(令和2年7月号) 西郷どんの教えその19
新型コロナウイルス感染症の脅威の中、早いもので半年が過ぎ、いまだワクチン開発も道半ばの状態。「新しい生活様式」の定義がなされ、町民はもとより全ての国民がこれからの社会の在り方を模索しているのではないだろうか。このような事態の時にこそ、「人の意見を聞くこと」が重要である。西郷さんもこのような事態の時には、「己を足れりとせず」と言っています。
上に立つ人も、下にいる人も共に、己が完全無欠であるという人などいるはずがないのに、どういうわけか錯覚に陥るのか、自惚れてしまうのか、自ら反省することを忘れてしまう。上下共々に自分はいまだ未熟者であることを認識することによって前に進むことができるのです。「己の愚かさを考える」という入り口は誰にでも用意されているものですが、なかなか見えないものなのです。
新型コロナ感染終息の出口が見えない今、対策の入り口を間違えないで進むことを含め、生活の基本的な所作が大切だと思います。
西郷さん曰く、「謙虚で素直な気持ちを忘れずに、みんなの意見を聞くこと」このことが、いい家庭をつくり、よい町になっていく。
友達に自分の考えを素直に言えますか?(令和2年6月号) 西郷どんの教えその17
日本の幕末、維新の社会は、「攘夷」を掲げ新しい国づくりを目指した志士たちによって生まれた。けっして黒船の来航等、諸外国の強大に屈したわけではなく、国民の先覚者と有識者が「国をもって斃るる精神」を奮い起こして外国に対したからである。「攘夷」とはただの排外主義ではなかった。自ら正道を踏み、民族的誇りを持つと同時に「敵の武器を奪ってわが武器とする抵抗運動であった。」と、西郷さんは言う。
正しいことを行い、相手を思いやる心がなければ、友達を良い方向に導くことはできない。友達を怖がり、ただ、仲良くすることだけを考えて、自分の考えを曲げたり、言わなかったりして付き合うようでは、よい学校やクラスをつくるどころか、友達関係は崩れ、最後には学校やクラスが壊れていくことにつながっていく。
「仲良しだけじゃだめ。お互いに良い方向に進んでいるかが大事」
叱られることを恐れていませんか?(令和2年5月号) 西郷どんの教えその16
「節義廉恥は国を維持する道」が原文であるが、正しい道義の必要性と廉恥の心がけを教えている。
今、世界中を震え上がらせている新型コロナウイルス。WHOは、新型コロナウイルスについて人為的に作成されたものではなく、動物が起源であると言明した。まさしく自然発生ということであり、この頃多くなっている自然災害等とも相通ずるように感じる。私たち人間は、自然と共に生活し社会を築いている。
しかし、文明社会の発展と共に機械を発明し、ますます便利な情報化社会を想像している。悪いことではないと思われるが、この新型コロナウイルスに対峙しているこのとき、今後の社会がどう変わるのか、さらには、変わらなければならないのかを考えなければならない。西郷さんは、「廉恥の心がけ」として、自分の利益だけを求めると卑しい心が強くなり、道義とか恥といったような道徳を失ってしまう。一番恥ずべきは、知っていて実行しないことである。廉恥を失うことが国を失う。と、言っています。
生命誌研究者・中村桂子さんの新聞論説の中で、新型コロナウイルス対策は一人一人が責任を持ち「手洗い」をすること。そして、この「手洗い」からこれからの社会が想像できると言っています。「私たちは、ウイルスが存在する自然と向き合って生きている。自然とは、具体的には地球である。一人一人が自分の役割を意識して行動することで地球とつながる。」
新型コロナウイルスのワクチン開発は必要であり、待ち遠しい。が、今は何よりも「手洗い」をしましょう。
流行を勘違いしていませんか?(令和2年4月号) 西郷どんの教えその11
文明開化が進む明治初期の情勢と背景は、西洋文明を称え崇拝するという世情が極めて強かった。西洋文明によって、科学の進歩、新しい産業の芽生え等に大きな期待感がもたれていた。また、その反面西洋の文明の名のもとに、植民地化を進め、有色人種の差別化も行われ、強引な交渉などによる不平等な外交も行われていた。そんな時代の流れの中で、西郷さんは疑問を持ちながら時代の荒波を感じていたのかもしれません。前回のコラムに続いて、国づくりの考え方の基本についての話になりますが、目新しいことを取り入れることを「文明」ということではないと西郷さんは言っています。文明とは、「道に叶ったことが世に広く行われることを称えて言う言葉であって、建物が荘厳であるとか、外観が華やかであるとかを言うのではない。流行ばかりを気にして行動することはどうなのか」と問いかけています。
「流行って先を行くことじゃない。どれだけ正しい行いができるかだ」
親や周囲に感謝する気持ちを持っていますか?(令和2年3月号) 西郷どんの教えその10
まちづくり・くにづくりに最も大切なのは「人智の開発」であると西郷さんは言っています。人智の開発とは、人の知恵・知識を新たに開発し、心を開き目覚めさせることですが、これこそが人材教育の目的であり、それは「愛国忠孝(国を愛する、親に忠孝の道を尽くす)」という心を開かせるということです。よく学び、知恵を磨くことは、親への孝行であり、それは、よい学校をつくり、よい町・国をつくることにつながる。「見た目はどうだっていい。心の豊かさ、やさしさが大事」と文明開化が進む明治初期に、西郷さんは日本の行く末を心配していたのかもしれません。先進文化国家とも見えた諸外国に一時でも早く追いつき、追い越したいと思って国づくりは進められました。しかし、焦りにも似た近代化が反動的にもたらす我が国に及ぼすマイナス指向現象に予見と警告を述べられたのであったと言われています。AIの発達、ICTの普及が進み、5Gの時代が迫ってくる今、これからの社会・町はどうなっていくのでしょうか? 少子高齢化が進む今こそ、「町づくりの基本を忘れるな」という西郷さんの言葉が身に染みるのです。如何なる時も基本を忘れず、愛国忠孝の心を開くことが大事で人の心も町も豊かになると感じるのです。
今も、大人になっても変わってはいけない大事なことは?(令和2年2月号) 西郷どんの教えその9
忠孝・仁愛・教化の3つの道徳は政事の基本である。そして未来永劫世界のどこにおいても欠くことのできない大事な道である。もとより道というものは天地自然のものであるから西洋とか東洋とかの区別はないものである。
一、 忠孝。つまり、学校では先生の言うことをよく聞き、家では親を大事にし、自分の役割をきちんと行うこと。
二、 仁愛。つまり、人には優しく、思いやりの心を持つこと。
三、 教化。つまり、友達や下級生には正しいことを教え、良い方向へむかう
ように手伝ってあげること。
この3つは、学校でも社会でも人間が生きるために必要な道徳の基本であり、大きくなって働くようになっても変わらないし、変わってはいけない大事なことである。
社会は人間の集まりであり、人間性のある人間味のある人が一人でも多くなることが、世の中を進歩向上させることにもなる。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
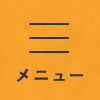
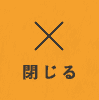

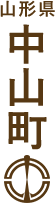




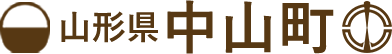
更新日:2023年09月01日