ひと・夢・まち 町長コラム(令和4年)
(広報なかやまより)
曇り空に広がるサムライブルー~新年に向けて~(令和4年12月号)
12月2日午前6時・師走の寒い朝、サッカーW杯予選・スペイン戦。負ければ予選敗退という場面での逆転勝利。どんよりとした空に、すっきりとした青空が広がるような一日の始まりとなりました。選手一人ひとりが祖国の威信をかけて戦い「自分はできるという絶対的プライド、あきらめない気持ち」が勝利を呼び込んだ試合だったと思います。
2022年はさまざまなことがありました。新型コロナウイルス感染症が確認されてから3年が経とうとしている今、感染拡大が第8波に入り大変な生活が続いています。ワクチン接種の一定の有効性もあり重症化率も低くなってきているようですが、まだまだ油断は禁物です。しっかりと守ることが攻撃力をアップさせると、森保ジャパンは実証してくれました。基礎体力をつくり自己免疫力を高め、厳しい冬を乗り越えていきましょう。
改めて「スポーツの力」に感謝し、町民の皆さまが輝かしい新年を迎えられますことを祈っています。
山形県少年の主張大会~今伝えたい私のメッセージ~を聞いて(令和4年11月号)
第61回山形県少年の主張大会(9月開催/山新10月6日掲載)をユーチューブで視聴しました。 論語/孔子のことばに「後生畏るべし(年が若く気力もあり、将来への可能性をもっているから、畏敬すべきである)」がありますが、まさしく、現代の中学生に改めて感服し、安心したところです。
現在の学校教育は、ITの導入により積極的に情報を活用できるようになり、あらゆる問題・課題が人工知能(AI)によって解決できるような時代を迎えていますが、彼らの主張からは、事実を見つめる力強い心の声が伝わってきました。戦争問題・自分の夢・他人への思いなど、一つ一つのテーマにしっかり向き合っている彼らは、これからの社会の希望であると感じることができました。
彼らと同年代の当時16歳だったグレタさんは、我々大人に対して「温暖化対策」について要求し、世界中の若者たちを動かし、「持続可能な世界」を次世代に残すための課題を提言しました。
選挙権を持っていない若者も、今の社会に対して大いに疑問を持ち、提言する権利と勇気を持ってまちづくりに参加することは、重要であると改めて感じています。
大先輩と共にウォーキング(令和4年10月号)
去る9月18日、3年ぶりに一大イベントである「元祖芋煮会in中山」が開催され、町民の皆さんとスタッフ、そして多くの来町者の方々とで会場が一体となり、盛り上がることができました。厚く御礼申し上げます。
今年は「第1回中山すももウォーキング」の同時開催もあり、多くの方に参加していただきました。私は6.5キロメートルコースに参加し少々疲れましたが、道中一緒になった山辺町からの参加者(人生の大先輩・83歳)と共に仲秋の中山町の田園風景を楽しみながら1時間20分で完歩することができました。 大先輩の足取りは軽く、歩く姿勢・若々しい筋肉美は、彼が毎日続けているというウォーキングの賜物と感服し、体調のすぐれない奥様とも一緒に歩きたいと願っている言葉には、人生を共に歩んできた優しさを感じることができ、秋の風と共に清々しい時間でした。
約3年におよぶコロナ禍を過ごす中で、人と人の交流・つながり・絆という言葉を改めて体感できた一日でした。「来年もぜひ参加したい!」との多くの声に、町の活力を実感すると共に、大会意義の重要性を感じています。
来年も皆さんで盛り上げていきましょう。
良い言葉によって心が晴れる(令和4年9月号)
先月の豪雨時(8月3日~4日)に中山中学校に避難された方より感謝のお手紙をいただきました。 高齢者と乳児もおられる家族の方で、コロナ感染の心配、足の悪い曾祖母の休める場所や授乳できる場所があるのか等々不安を抱えながらの避難のようでしたが、テントなどの設置やスタッフの夜を徹しての気持ち良い対応で大変助かったとのことでした。そして、「ある格言に「良い言葉によって心が晴れる」という言葉があるように、設備面の充実も大切ですが、やはり心を安化させるのは気遣いの言葉だなと感じました。」と寄せてくださりました。
町はおととしの豪雨災害の教訓を生かし、避難施設の環境整備を含めた地域防災計画を見直しました。中学校と総合体育館の両避難所では、プライバシーの確保とできる限りの感染予防対策として、二人用のテントと簡易ベッド・椅子などを用意しています。受付時には町民の方の状況把握に努め、家族に合った場所の提供、避難者の気持ちに寄り添った対応に心掛けています。
気候変動による豪雨災害が多発している昨今、防災強化は重要施策です。そのような中での今回のお手紙は、職員並びに関係者にとって大変励みになりました。投してくださった方へ私からも感謝です。そして、ボランティアで手伝ってくれた高校生にも感謝です。
夏に咲く大輪の花(令和4年8月号)
JR羽前長崎駅西側の農地に先月中旬、ひまわり迷路がオープンしました。高さ2メートルほどのひまわりが咲き誇り、町内の園児と今年デザインを担当した長崎小6年生が歓声を上げ駆け回っていました。 ひまわり迷路は、2017年の当時5年生だった長崎小児童が町のPRにと提案された事業で、毎年約50アールの農地に子どもたちが迷路を設計し、豊田大豆転作組合が中心となり作っています。 大人の背丈以上に伸びた迷路は決して容易いものではなく、大人も子どもも大いに冒険心をくすぐられているようです。当時の子どもたちのまちづくりに対する提案には、未来に対して背を向けず前向きに進もうとする力と、生まれ育った故郷への愛着を感じたのを記憶しています。
ひまわりの種まきは、甲子園大会県予選が行われている時期に満開になるように計画され、毎年駅を降りた球児、応援する仲間たちを迎えています。勝ち続けた1校はもちろん、敗れた42校の選手の心の中にも夏の大輪は咲くのです。
いろいろな思いを馳せて撮られた写真の中には、太陽に向かって咲こうとするひまわりの凛とした姿と、彼らの想像しきれない未来への希望とが写し出されているだろうと思っているのです。
第二の故郷(令和4年7月号)
6月上旬、都市対抗野球第二次予選東北大会が県野球場で開催されました。
地元のきらやか銀行も県大会を勝ち抜出場決定していたところに、私に始球式の依頼があり、快く引き受けました。きらやか銀行は、ここ数年間で二度東京ドームでの全国大会に出場している強豪チームですが、今年は惜しくも全国大会出場は逃してしまいました。 練習拠点が中山町で、主力の小島投手は元長崎支店の行員でもあり、今後の活躍に大いに期待しているところです。
今回の大会では、新たな驚きの情報も舞い込んできました。福島県代表チームのメンバーに中山町出身者がいるとのこと。詳しく伺うと、十一年前の東日本大震災で被災され中山町に一時避難していた佐藤翔君でした。当時小学生だった佐藤君は、中山ジュニア野球スポーツ少年団、中山中学校と町の野球チームで活躍し、東海大山形、八戸学院大学で野球を続け、卒業後は福島県に戻り社会人野球クラブチーム(エフコムベースボールクラブ)に所属、今回福島県代表チームの一員として再訪町となったのです。たくましい身体と清々しい眼差しには、再会の喜びと未来への期待が感じられました。
「絆」と一言では言い表せない 「奇跡」を感じつつ、彼の「第二の故郷」 中山町からエールを送り続けたいものです。
学ぶことの本当の意味を知っていますか?(令和4年6月号) 西郷どんの教え その41
2019年5月から3年、西郷隆盛の曾孫である西郷隆文氏が、「南洲翁遺訓」についてわかりやすく青少年向けに書かれた 「西郷どんの教え」全四十一章の中から三十章の遺訓を紹介させていただきました。いよいよ今回は最終章です。
「よく勉強し、人にも好かれ、心が穏やかな人も、何か事が起こった時にその対応ができない人は、木で作った人形のようなもの・・だから普段の準備が何より大事なことだ。つまり、勉強というのはただ、文章を読んだり書いたりすることではなく、何かが起こったときにこれを上手に処置できる才能を磨くことを言うんだ。スポーツも道具を上手に使いこなすことではなく、試合の相手の事をよく知ってこれに勝つ才能と知恵があるかどうかが大事なことなんだ。」と言っています。
西郷さんは、維新という時代の中で常に勝敗を意識し、「勝つこと」が「生きること」と諭していると感じていましたが、最後にとても切ない気持ちで「そうであろうか?」と疑問を持ちながら、問いかけています。
私は、学ぶこととは疑問を持ち問いかけること、そして考えてみることであり、学び続ける喜び (探究心)を持ち続けたいと思います。
勉強だけが大事と思っていませんか?(令和4年5月号) 西郷どんの教え その37
真心厚く、考えて行動していますか?(令和4年4月号) 西郷どんの教え その36
今回の西郷さんの教えは、「真の機会」についてです。
「世の中の人が良く 「好機をつかんだ」というのは、多くはまぐれ当たりのことを言うものである。 本当の機会というものは道理を尽くして考えた上で行い、そして時の醸成を明らかに見極め動くときにつかめるものである。 平生から天下国家を憂うる誠が厚くないのに、ただ時のはずみにのって成功した事業というものは決して永続きはしないものである。」と教えています。
脱炭素社会に向けて一歩踏み出し、新型コロナウイルス感染症の対策を講じているさなか、信じがたい出来事が世界を震撼させています。
SDGs : だれ一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標として掲げ、2030年を達成年月日としています。当時16歳だった少女グレタ・トゥーンベリは、地球温暖化の弊害を全世界の人々に訴えかけています。
私たちが共存しているたった一つの地球、天を敬い、人を愛する環境を創造していかなければならないと痛切に思う今日この頃です。
いつも堂々と公平にできていますか?(令和4年3月号) 西郷どんの教え その35
150年前に、西郷さんは、組織の総大将たるものの心得として守るべきことを次のように述べています。
「人をごまかして、見えないところでこそこそ動く人は、たとえそのことが出来上がったとしても、醜いことだとすぐわかるものだ。 人に対しては常に公平で真心をもって接し、公平でなければ、人の心をつかむことはできない。」
先月のコラムでは、「未来の子どもたちのために新型コロナを克服し、かけひきのない安全で平和な社会を残す責務を強く感じる」と紹介させていただきました。 新型コロナウイルス感染症もオミクロン株という変異種の出現により収束も見えていない今、2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻は全世界に衝撃をもたらしています。
隣人を思い、争いのない平和な暮らしを享受するためには、ごまかしのない公平至誠の心を持つことが大切であると、つくづく実感させられます。
交渉上手になっていませんか?(令和4年2月号) 西郷どんの教え その34
今和4年も早ひと月が過ぎ、新たなる目標が見えてきている頃でしょうか。 平成30年6月からコラムのテーマとしてきた西郷どんシリーズ「西郷どん十の訓え: 西郷家の家訓」からスタートし、今日まで西郷さんの信念を紹介してきました。「西郷どんの教え」は全4章に加え、追加18章で構成されています。 これから先もしばらくの間、150年前に語ったとされる西郷隆盛の言葉に耳を傾けていただければ幸いです。今回は、「かけひきは普段は使わないほうが良い。 かけひきしてやったことは、その結果を見ればよくないことがはっきりわかるもので、必ず後悔することになる」という言葉をご紹介します。
コロナ禍の状態が続いている今、「何を成すべきか?」一人ひとりが考え、行動することが大切な対策の一歩と思っています。
私たちが生活している社会は、さまざまな歴史的背景を経て、今があるわけです。未来の子どもたちのために新型コロナを克服し、かけひきのない安全で平和な社会を残す責務を強く感じるのです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
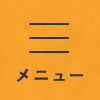
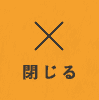

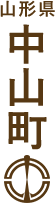




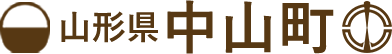
更新日:2023年09月01日