学校の栄【まなびやのはえ】
学校の栄【まなびやのはえ】
「学校の栄」は、「まなびやのはえ」と読ませます。
これは、「豊田小学校の校歌」の3番目の歌詞に歌われています。
「学校(まなびや)」というのは、豊田小学校のことで、「栄」とは「誇れるもの、ほめられて自慢できるもの」ということです。
これを調べるに当たって、今から約20年前、地区の方々の手でまとめられた「中山町立豊田小学校誌」という「豊田小学校の歴史が詳しく書かれた1冊の本」を参考にしました。
この本を見ると、「学校の栄」とは、(1)校舎(何度も立て替えられました)、(2)豊田村初代村長永田亀次郎さん、(3)豊田小学校初代校長 小松景久先生、(4)校章、(5)校旗、(6)校歌、(7)誉の松、(8)高取山の八つがあげられています。
豊田小学校の「八誉れ」(ハチホマレ)といえばいいのでしょうか?
この「学校の栄」については、創立記念式の式辞で平成17年は「誉の松」について、18年は「校舎」についてお話ししました。今後も、創立記念日には順次、この豊田小学校の「八誉れ」についてお話したいなと考えています。
誉の末【ほまれのまつ】


「誉の松とは?」職員玄関の前にある3本の見事な松の木をいいます。幹が太くて枝振りがよく、3本の松がうまく調和し、どこから見てもとても美しく形作っています。この松の木が、「誉の松」と呼ばれ、豊田小学校のシンボルになってきました。
卒業生が母校を訪れるとこの松に手を触れられ、しばし小学校生活を懐かしむことが多いのだそうです。この誉の松は、風雪に耐え、豊田小学校の歴史をずっと見続け、登下校する皆さんや校庭で遊ぶ皆さんを見守ってきてくれたのだそうです。
それで、私が豊田小学校に赴任したときに、「校長先生より大事な木だそうですから、枯らさないようにお願いします。」といわれました。
さて、この松は、今の新しい校舎に立て替えられる(昭和56年)前は、今のグラウンドの真ん中あたりにあったそうです。そもそもこの松は、明治41年、豊田小学校ができてまもなく、小学校の高学年の人たちも手伝って学校の裏山などから運び出し、植えたものだそうです。
昭和56年に、今の新しい校舎ができあがったときに、グラウンドも整備しましたが、真ん中に大きな松の木があっては運動ができなくなるということで、切り倒すしかないと考えたそうです。しかし、このすばらしい松の木を切り倒すことに強く反対する人が多く、移動させることになったそうです。それが今から24年前です。

この大きな松の木は、すごく根も張っていて、移し替える作業は、とても大変だったそうです。当時最大のクレーン車2台でつり上げたそうですが、その重さで反対にクレーン車が地面にめり込んだといわれています。
やっとの思いで今の場所に移転させたものの、葉が赤くなり枯れてしまうのでないかと心配したそうですが、よく生き返り、学校で大切に手入れをしてきたし、卒業生も根元を踏んづけたりしないで大切にしてきたので、現在まで永遠の緑を保っているということです。
でも、最近なんだか弱ってきているのではないかという声が聞かれ心配です。今年も春、雨が少なくとても暑い日がが続いたので、葉が赤くなり心配をしました。それで、木のお医者さんに見てもらって、植木屋さんに軽く剪定をしてもらったり、実をとってもらったり、栄養剤をたくさんまいて、元気を回復してもらいました。
さて、この「誉の松」と名付けたのが、初代校長の小松景久先生だそうです。小松校長先生は、豊田小学校の卒業生が、誉れ高く育ち、優れた立派な人が次々に世に出るようにと願って「誉の松」と名前を付けたと言い伝えられています。
これが「誉の松」にまつわるお話です。
さて、皆さん、これからもずっと見守っていただけるように、この松を大切にしてきた多くの先輩たちを見習い、大切にしていって欲しいと思います。
そして、多くの先輩たちが一生懸命勉強してきたこの学校で、学習できる幸せをかみしめながら、楽しく充実した毎日を送ってほしいと思います。
(平成19年創立記念式 校長式辞より)
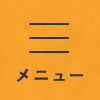
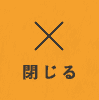

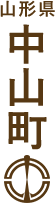




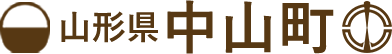
更新日:2023年09月01日