ひと・夢・まち 町長コラム(令和7年)
(広報なかやまより)
「くらし」をつくる (令和7年9月号)
戦後10数年後に生まれた私は、高度経済成長の中で育ち、気づけば、私たちの生活はますます便利になり、多くの物が店頭で買える世の中になました。私同様、そんな思いの町民の皆さんも多いのではないでしょうか。食料品、雑貨、衣料品に文房具。私たちの生活に欠かせないものですが、これらは私たちの「くらし」そのものではなく、私たちの「くらし」をサポートしてくれる便利グッズなのです。
そして、家族が衣食住をともにする家は、各家庭の「くらし」の基盤と言えるでしょう。その「くらし」の基盤を店頭の棚から商品を選ぶような短期的な買い物にしてしまうのではなく、長期的な視点で考えるべきではないでしょうか。家は雨風や暑さから身を守る単なる建物ではなく、家族のライフスタイルや価値観を反映する場所であり、住む人のニーズや将来のビジョンが詰め込まれた憩いの空間なのです。新築の家だけではなく、古い建物をリニューアルして造ることもできます。自分らしい家を家族皆でつくることは、「くらし」づくりの基本だと思います。
町では、昨年から中山町に暮らしながら感じている、町の「良いところ」「改善が必要なところ」「期待したいところ」などを聞いてきました。今年は、得た意見の中で最も多く上がった「なぜ?」を集めて「なぜなぜ大会議」を開催しました。今後は、住民皆さんで考えた改善策を町づくりに活かしていきたいと考えています。多面的で複雑なプロセスを経て、感情やライフスタイル、将来の視点を考慮して進められる町づくりは、私たち皆が各家庭で行っている「くらし」づくりの延長線上にあると思うのです。
「のむおにぎり(仮称)」って、何? (令和7年8月号)
梅雨はあったのだろうか?と感じられるほど雨が降らない暑い7月でした。そのような猛暑の中、今年も甲子園を目指しての高校野球県予選大会の熱戦が繰り広げられました。毎年さまざまなドラマや感動がありますが、今年は、山形南高等学校に関心が注がれる日々がありました。と言うのも、わが町に1年前から赴任している地域おこし協力隊の阿部美恵子さんが開発している「のむおにぎり」を同校野球部員が試飲しており、3回戦、準々決勝の2試合は逆転勝利!猛暑の中での終盤の集中力は「のむおにぎり」の効果があったのではと話題になったのです。試作品は、同校のほか、惺山高等学校女子野球部、中山ジュニア野球スポーツ少年団の皆さんからも試飲協力をいただきました。原料のお米は中山産の「はえぬき」を使っており、阿部さん曰く、時間がない時の栄養補給や保存食にお薦めとのことです。「スポーツとフルーツ 伸びゆく町 なかやま」をキャッチフレーズに掲げる町から、スポーツを支える一役として商品開発が進むことを期待しています。
平昌五輪カーリングの試合でハーフタイムに車座になってイチゴやリンゴ、ドライフルーツをほおばりながら作戦を話し合う「もぐもぐタイム」を想像させるような、選手をサポートできる取り組みは素晴らしいと思うのです。
長崎駅西口の「ひまわり迷路」は、今年も夏の高校野球に合わせたように見事に咲き誇り、人々の心を和ませてくれていました。当時提言・実施してくれた小学5年生は、高校3年生になりました。
「過疎」ではなく「適疎」のまちづくり3 (令和7年7月号)
三か月にわたり「過疎」と「適疎」について書かせていただきましたが、適疎(てきそ)とはどういう状態なのか ?この言葉自体は、1969年の「過疎社会」(米山俊直著)でも使われており、日本で一極集中が進み、過疎や過密が論じられ始めたころから存在していたようです。
先月、北海道「写真の町」東川町に視察に行ってきました。現在の人口は8000人、中核市・旭川市(人口 31万人)に隣接しており、わが町と立地条件が似ている町です。 20年前の平成の大合併時に、町民は、「東川らしさ」を選択し、合併せず、独自のまちづくりを目指しました。そして、町では 15年前から、まちづくりの理想像を示す言葉として「適疎」を使っています。町民にとって「適疎」とは、仲間と時間と空間の3つの「間」があり、人々の暮らしに「ほど良いゆとり」がある暮らしと語っています。
当町とは経緯は違えども、「らしさ」という響きは、全国に通ずる地方創生の根幹であると思う日々です。交通の利便性は町を形成する重要な要素です。その利便性を生かし、中山町に関係を持ちたいという人が増え、行ってみたい・住んでみたいという人が増えるような町にしていきたいものです。
日本遺産の構成文化財であるわが町の紅花まつりにも多くの方が訪れ、これから全国かぶと虫相撲大会、すももウォーキングと各種催しが続きます。そして、舟運ハブ港として発展してきた町、その地で生まれた「芋煮会」。多くの人々に自慢し、広めていくことは「中山らしさ」づくりになると思って います。
「過疎」ではなく「適疎」のまちづくり2(令和7年6月号)
先月、山形県の総人口が予測通り105年ぶりに100万人を割り込みました。そして、25年後の2050年には 71万人台になると予測されています。
国の基準による「過疎化」とは、その地域の人口が減少した結果、その地域での日常生活や生産活動が「一定レベルを維持することが困難」になった状態を指した言葉で、山形県の2/3ほどの市町村が「過疎地域」となりますが、中山町は現在該当していません。ただし、今年までの 10年間の増減率を見ると 11.2%の減少で、今後さらに減少率が高まることを考えると、30年を待たずして「過疎」となる予測です。ただ、その時は山形県のほとんどの市町村が「過疎」となってしまうことになり、市町村単体だけの町づくりではなく、より一層連携を強化された形が重要視されています。
さて、新しい年を迎え米価高騰をはじめ物価の高騰が生活に重くのしかかってきている中、さまざまな物品・工事・人件費等々の適正な価格について議論されていますが、わが町の基幹産業である農業について考えてみると、作物の生産・経営だけではなく、町が対峙している防災に大きく寄与しており、異常気象による大雨の受け皿としての「田んぼダム」は、町の生命財産を守る役目を果たしてくれています。そのような「おたがいさま」の互助精神は、少なからずこれからのまちづくりに必要になってくると思うのです。
国で定める「過疎」とは ? そして「適疎」とは ? 皆で考えてみましょう。
「過疎」ではなく「適疎」のまちづくり1 (令和7年5月号)
今月、山形県の総人口が100万人を割り込むとの見通しが示されました。1920(大正 9)年以来、105年ぶりとのことです。中山町においても自然減少はあるものの、転入者もおり減少率は低く、人口減少は緩やかに進んでいるのが現状です。しかし、1万人を割り込むときは、いずれ来ると思われます。
昨年度、長崎小学校6年生と給食をともにしたとき、「人口減少について町長さんはどう思っていますか ?」という、鋭い質問をしてくれた児童がいました。丁度、給食終了後は掃除の時間であったこともあり、一人ひとりの掃除の責任範囲について話をしました。「 30人のクラス人数が 20人になったとき、一人ひとりの責任は増えてくるよね」という話をすると、「なるほど ! 」という反応を示しながら各々が考えていました。「町の広さ、道路の長さ、建物の数などは変わらないけれども、維持していくためにはお金が必要。大きな問題だから一緒に考えて いこう」と。
子どもは町の宝。これからの町づくりについて談笑しながら、真剣に町の未来について考えている子どもたちを誇りに思い、希望が見えたひとときでした。
論語「學まなびて時に之これを習う 亦また説よろこばしからずや」・・・(令和7年4月号)
4月、新たな生命が芽吹く季節です。
各方面で躍動するスターのニュースも次々と飛び込んできます。海の向こうのメジャーリーグでは、大谷翔平選手、山本由伸選手に続いて、佐々木朗希選手が 同じドジャースに加わり新たなステージに挑戦しています。自分の夢を叶えるために新たな道を選択し歩んでいく姿は、私たちに希望と勇気を与えてくれています。
孔子の論語の首章に、「『學(まな)びて時に之(これ)を習う亦説(またよろこ)ばしからずや』(学んだことを繰り返し練習するうちに理解が深まり向上していく。これはなんと嬉しいことではないか)」という格言があります。前記の彼らの現在があるのは、才能はもちろんのこと、それ以上の努力の積み重ねの賜物と改めて痛感するのです。
新年度を迎えるこの瞬間は、まさに新たな始まりを象徴しています。我が町の各方面でも新たな動きや出会いがあり、緊張感や不安とともに期待にあふれる芽吹きの時です。過去の経験を糧にして、新たな出発をともに喜び、学びを繰り返しなが ら一歩一歩未来に進んでいきましょう。
学校給食とお箸について思うこと・・・(令和7年3月号)
「中山町の給食は美味しいね」という嬉しい言葉を耳にすることが時々あります。私は毎年、小・中学校の最終学年全クラスの子どもたちと、この美味しい給食を共にしています。とても貴重な楽しい時間で、子どもたちの好奇心や純粋な反応に触れることができ、心が温まるひとときです。
学校給食は、明治22年(1889年)山形県鶴岡町(現鶴岡市)の小学校で貧困家庭の児童を対象に行われたことが始まりとされています。国会では学校給食無償化が議論されていますが、我が町では完全給食無償化が実施されており、 10年前からは温かいご飯の提供も行っています。
このような中で「お箸」だけは家庭から持参していただいています。お箸は、私たちの生活に深く根ざした文化的な道具であり、食と家庭をつなぐ命の架け橋だと思うのです。箸の持ち方の礼儀から始まり、「いただきます」「ごちそうさま」の言葉で食材や料理を作ってくださった方に感謝し、家庭でも学校でも温かいコミュニケーションを助けてくれる大切な「お箸」なのです。
先月、中央公民館にて東京藝術大学名誉教授の三田村有純先生を講師に招いての箸作りが催されました。先生は漆芸家であり、旧柏倉九左衛門家に伝わる漆器類の歴史的価値を検証していただいている方でも あります。参加された方々は、生竹で成形された箸(各人に合ったサイズ: 一咫(ひとあた))に着色し、先端には漆塗りが施されているマイ箸作りを楽しみながら、食とお箸の大切さを学んでいました。日本には、素晴らしい食文化があると改めて思うのです。
「芋煮会」は、人と人を結ぶ町の宝・・・(令和7年2月号)
令和7年巳年が動き出しました。新年早々、北前船交流拡大機構の新年会に参加させていただく機会に恵まれ、東京に出向きました。日本海に面している寄港都市がメインの会議なのですが、最上川舟運で栄えた我が町のこと、一昨年に完成したレトルト食品「北前いも煮」のことなどを紹介したところ、参加者150名分の記念品として「北前いも煮」の注文を受けることとなり、当日は、初めて出会う人々にPRビデオを流しながら中山町を紹介し芋煮会の醍醐味を広めてくることができました。わが町の芋煮会は単なる食文化にとどまらず、地域の人々の結びつきや観光資源としての役割を果たしていることを改めて感じることができ、「芋煮会発祥の地」として、とても誇らしく感じた一日でした。
今後のまちづくりにおいて「芋煮会」は、1文化の保存と継承、2観光資源としての活用、3地域住民の参加促進、4地域産業との連携の要素を組み合わせることで、町独自の文化や歴史が未来への豊かな地域社会の構築につながると思っています。
中山町誕生70周年記念事業として、10月2日が「芋煮会の日」と記念日登録され、新たなる一歩を踏み出しました。年初めに起きた思いもかけない人との出会いが、人と人を結び、町と町を結んでいき、地域が豊かになっていくのだと思っています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
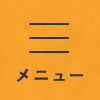
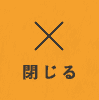

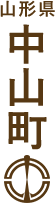




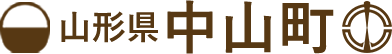
更新日:2025年09月15日