中山町の伝承芸能
町に伝わる伝承芸能
中山町では、様々な信仰に基づく豊かな民俗文化が残っており、以下の4つの伝承芸能を町の無形民俗文化財に指定しています。
| 名称 | 伝承地区 | 町指定年月 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| 達磨寺田植踊 | 中山町大字達磨寺地区 | 昭和61年4月 | 4月 |
| 小塩御福田田植踊 | 中山町大字小塩地区 | 昭和61年4月 | 閏年の2月頃 |
| 土橋獅子踊 | 中山町大字土橋地区 | 昭和61年4月 | 5月 |
| 中山町川向金比羅樽流し | 中山町大字長崎川向地区 | 平成26年3月 | 6月 |
達磨寺田植踊
(だるまじたうえおどり)


江戸時代の若者が熱中した田植え踊り
田の神をまつり稲の豊作を祈願したのが「田植え踊り」ですが、 田植え踊りには少なくとも2つの系統があります。1つは「弥十郎系」で、もう1つはテデ棒をつく「テデ系」とよばれるものです。
「達磨寺田植踊」は村山地方のテデ系田植踊りの典型的なものです。言い伝えでは元禄時代より伝わったといわれる豊作を願う踊りです。天保年間には農村娯楽として盛んに踊られたらしく、天保15(1844)年の古文書には農繁期に踊りの練習に熱中しすぎて田植踊りを謹慎された旨が記されています。当時の田植え踊りを物語る貴重な古文書です。
大正時代以降は達磨寺地区の鎮守・八幡神社の祭礼(8月15日)に奉納されていましたが、現在は、4月15日に「お達磨の桜公園」で華やかに咲き誇る桜の下で踊られています。
小塩御福田田植踊
(こしおごふくでんたうえおどり)




葉山信仰と田植え踊りが合体した県内唯一の行事
県下には数多くの田植踊りがありますが、小塩地区の田植踊りは「御福田行事」と「田植え踊り行事」がいつの頃からか合体した、県内でも唯一の貴重な行事です。
「御福田」は葉山信仰に係る行事で、お葉山坊(法印)が小塩地区内の祝い事のあった家(分家した家や新築した家、嫁を娶った家など)を巡り、祭文をあげて五穀豊穣と無病息災を祈祷します。虫除けの御札を渡して法印が去るのと入れ違いに、今度は「田植え踊り」の一団が繰り込んで、テデ衆や花笠を被ったソトメ(早乙女)等がお座敷で賑やかな踊りを披露します。
旧正月二十日の行事とされ、現在は4年に一度の閏(うるう)年に踊られています。
※「御福田」はお供えの小さな丸餅を御福田と称することに由来します。
土橋獅子踊
(つちはしししおどり)


曹洞宗本山「永平寺」免許皆伝の獅子踊り
「土橋獅子踊」は、江戸時代初期の寛文12(1672)年に土橋の佐藤藤作という人が伊勢参りの帰りに福井の曹洞宗本山「永平寺」で習いおぼえ、皆伝の巻物をうけて帰ったことが始まりとされています。元来「聖霊菩提踊」とよばれ、祖先の霊を供養し、家の永代繁昌を祈願するための踊りとされています。天保13(1842)年にはこの踊りが高擶村(天童市)に伝えられています。
現在は、毎年5月3日に土橋地区内の玉昌寺・山門前と民家の庭先で踊られます。また、旧暦7月7日には山寺立石寺の磐司祭で奉納の踊りをします。こういった山寺で奉納される獅子踊りの中ではもっとも古い形をとどめているといわれています。明治41年には、大正天皇が山形行啓された折りには山寺でご高覧にあずかりました。以来、県下を代表する獅子踊として様々な公開演舞でも活躍しています。
獅子踊りについて
獅子踊りの「獅子」とは日本に生息するイノシシ、シカ、カモシカなどの野生動物を意味します。踊り手はそれらの動物を模した被り物を被り、笛や太鼓に合わせて踊ります。獅子踊りは山の精霊(神)が里へ祝福に訪れる形がもとで、豊年踊りともいわれています。これは山の神が同時に農業の神であったからです。農業の神の祝福をうけるとともに、その威力によって農作に害をおよぼす悪霊が鎮圧され、豊作がもたらされるという信仰に発したものでした。
山形県の獅子踊りは、大きく置賜系・村山系・最上系・荘内系の4つに分けることができます。村山系の獅子踊りは、5人の「獅子」に女装の「ササラスリ」と、少年の「鉦(かね)打ち」などがつくものと、土橋のように腹太鼓をつけない長幕の獅子だけのものとがあります。また、村山系の獅子踊りは山寺立石寺の磐司祭(ばんじさい)で舞う習わしがあります。
中山町川向金比羅樽流し
(なかやままちかわむかいこんぴらたるながし)
概要



樽流し実施場所
最上川に樽を流して水難事故がなくなるようにと願う長崎川向地区に伝わる伝統行事『中山町川向金比羅樽流し』。平成25年7月に有志による保存会が設立し、平成26年3月に町指定無形民俗文化財に指定されました。
毎年6月1日には恒例の『樽流し』が行われています。最上川左岸にある金比羅堂で厳かに神事が行われた後、岸辺に移動して酒を入れた樽としめ縄を最上川に流し、水難事故の防止を祈ります。
全国でも珍しく、県内に唯一残る樽流しの風習
昔から海辺や川筋に住む人々、航海や舟運に関わる人々は、水の神「金比羅様」に対する畏敬の念をもっていました。その水の神への信仰が金比羅信仰です。その本拠地は香川県の金刀比羅宮にあり、金比羅信仰は江戸時代中期頃から全国に広まっていきました。
この時期、山形県では最上川舟運が盛んでしたが、日本三大急流の最上川では水難事故が絶えませんでした。そんな舟運の安全や水難事故の防止を願い、当時は中山町を含め県内各地で樽流しの風習が見られました。
しかし、時代の流れとともに樽流しは次第に廃れ、いつしか中断。今では「金比羅樽流し」の風習が確認されているのは、県内で唯一、川向地区のみになっています。
伝統行事継承に向けて保存会を設立
川向地区の樽流しは平成18年頃まで地区を挙げて実施してきましたが、金比羅講中の減少等が理由で中断。その後は「水難事故を起こしたくない」という思いから、白田ヤノさん(桜町)が一人で樽流しを続けてきました。
これを知った町内の有志が伝統行事の復活・継承に向け「保存会準備委員会」を組織。平成25年5月に8年ぶりに樽流しを復活させ、その2か月後、「準備委員会」から正式な「中山町川向金比羅樽流保存会」(鈴木昭十会長)を設立しました。会員数は22名。県内に唯一残る樽流し行事を守り、後世に伝えようと本格的な継承に乗り出しました。
町指定無形民俗文化財に指定
このような動きのなか、中山町としても地域に残る貴重な文化遺産を後世に継承していきたいことから、平成26年3月7日に「川向金比羅樽流し」を中山町指定無形民俗文化財に指定し保存に乗り出しました。
町が無形民俗文化財を指定したのは、達磨寺・小塩御福田田植踊、土橋獅子踊に次いで4件目です。
お問い合わせ先
中山町教育委員会教育課生涯学習グループ(文化財担当)
電話番号023-662-2175
この記事に関するお問い合わせ先
〒990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎6005番地
電話番号:023-662-2175
ファックス:023-616-6875
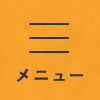
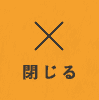

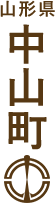




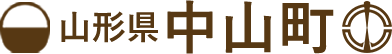
更新日:2024年02月02日