ひと・夢・まち 町長コラム(令和5年)
(広報なかやまより)
楯の大イチョウ(令和5年12月号)
12月号掲載の原稿執筆中の今日(11月25日)、粉雪が舞い降りた。平年より9日遅い初雪は、去年よりは5日早いという。私の不確かな見解なのかもしれないが、毎年、楯の大イチョウの葉の状況が初雪の時期を示す基準となっています。と言うのも、先人から受け継いだこんな「言い伝え」があります。「楯の大イチョウの葉っぱが落ちると雪が降り始める」。何の疑いもなく、またこの季節が訪れたなぁと、子どもたちと一緒に登校しながら眺めていたのです。ところが今年は、黄色く色付いたイチョウは落葉もせず勇敢にそびえている姿があり、粉雪が舞っている風景は、美しさ以上に不思議の感に打たれるのです。
楯の大イチョウは中山継信氏居城長崎楯(約640年前築)本丸内の庭前にあり、樹齢500年以上といわれています。先に述べた「言い伝え」はいつ頃からの話なのかはわかりませんが、自然現象の変化が気になる時代になってきています。
今年は暖冬という予報もあり気が緩みがちになってしまいますが、永年立ちつづけている大イチョウを眺めながら、一年を振り返り、町民の皆様が輝かしい新年を迎えられますことを祈っています。
後生畏るべし(論語(ろんご) - 子罕(しかん))(令和5年11月号)
当町の小学校・中学校では、数年前よりGIGAスクールが導入され、タブレットを活用しての新しいICT環境のもと授業が行われています。そして、それらを活用して「町づくり」について企画・提案する授業があり発表会が催されています。5年前より始まった「ひまわり迷路」もその一提案で、豊田大豆組合の方々の協力により実現したものです。子どもたちの企画は、一案一案が「自分たちが住んでみたい未来の町の姿」で感心させられます。このような中、10月初め高校生のグループによる「長崎駅待合室を明るくしよう」というプロジェクトが立ち上がり、ハロウィン装飾をしてくれました。来月はクリスマスに向けて思案中のようです。待合室が利用者の集う明るい空間になることを期待しています。
新型コロナ感染症5類移行後、先月から小・中学校への給食訪問を再開しました。久しぶりに児童生徒と給食を共にし、さまざまな質問もあり子どもたちの伸び伸びした生活を感じることができ嬉しいひと時でした。わが町には高校はありませんが、小・中学校で町を知り、未来を創造することを学んでいると感じ、頼もしい限りです。大きく羽ばたいてほしいものです。わたくしたち大人は、子どもたちの学びの権利を守り、環境を整えていかなければなりません。
孔子のことばの中に、「若い者は、将来、どこまで伸びていくかわからないほどの可能性に満ちている」と、述べられています。そして、「後から生まれて来るものには、畏敬の念を払うべきである」と。
空き家(令和5年10月号)
前回に続き空き家についての思いです。振り返ってみますと、空き家のことを戸(子)と表現し、まちづくりの課題の一つとして捉え、就任時から対策を講じてきました。
「わが町に 現在150戸以上のアキヤが生息している
あの戸もこの戸も 人間が造った生き物である
ただ、自ら動くことはできない 静かに佇んでいる
彼らには歴史と文化の匂いがする
ただ、時が進むにつれ病んでくる
決して死んでいるわけではない
………… 中略 …………
いま ひっそりと佇んでいるあの戸もこの戸にも
もう一度 息づかせるチャンスを与えたい
もう一度 彼らも生きたいと思っている
アキヤは まちにとって負の財産ではない
アキヤを元気にして まちも元気にして
人も楽しくなる
アキヤ・空き家は まちの財産です」
コラム2015年10月号より
空き家問題は深刻です。現在空き家は増え続け、全国には1千万戸以上の空き家が存在するとの調査結果が出ています。町としても空き家バンク制度を作り、移住対策にも力を入れているところです。国の制約、個人の権利等でなかなか進まない現状にありますが、今後とも力を入れていきます。来年4月からは相続登記義務化がスタートします。空き家でお悩みの方は、まず空き家バンクへの登録をお願いします。
異常気象による暑さの中で、空き家に思うこと(令和5年9月号)
例年にはない暑さの中、住む人がなく朽ちていく空き家を見ると、人間同様、生きるための水を欲っしているようです。国道458号沿線に建ち続け環境問題にもなっていた空き家(特定空家)が、このたびようやく解体されました。建物所有者の所在確認の難航などが代執行の遅れとなっていました。このように所有者から見捨てられた家屋は、外壁・屋根が飛ばされ、露わとなった木材は朽ち果て崩れ始め、害獣の棲家となってしまいます。反面、まだまだ住み続けることのできる空き家も多く、生き続けることを望んでいるようです。
現在中山町に存在する空き家の中で、利用可能な家屋は6割強という調査結果が出ており、町では空き家バンクへの登録を推進しています。登録制度を利用し、移住定住補助金・リフォーム補助金を活用し、移住された方も多数いらっしゃいます。求めたい人にその物件の情報を広く公開し、使える建物はできる限り改築工事等(リノベーション)を施し、次世代への引き継ぎをしていただきたいものです。
利活用可能な建物は、年代物であっても生まれ変われば美しさは蘇ります。そのためにも町民の皆様からはぜひ空き家バンクへの登録をよろしくお願いしたいと思います。所有している空き家をどうしようかと悩んでいる方々とは、いつか直接お話をうかがう機会をつくっていけたらと思っています。
紙書籍のぬくもり…(令和5年8月号)
自宅の書棚にふと目をやると、懐かしい背表紙が目に入ってきた。色あせた表紙、そしてタイトルには今『地球』が危ない」、その日その時になぜ目に留まったのかは定かではないが、手に取り開いてみた。
34年前に発行された書籍で、私が30歳を過ぎたころに求めたもののようだった。オゾン層の破壊を原因とする異常気象による地球の危機が書いてあるのだが、改めて再読すべきと思う内容だった。地球環境問題の重要性を感じるとともに、この書籍との再会を通してデジタル化が進む社会についても思うところがあった。学生時代から貯めこんだ建築雑誌も処分しきれていない。再び読むことはないだろうなと思いつつ、これらの本も背表紙を見ると中に掲載されている建築が蘇ってくるのである。部屋の中に置かれてある背表紙のタイトルだけが見えている紙書籍は、間違いなく自分の所有物として存在し、部屋の空間を構成している重要な要素になっているようである。
利便性、効率化が進んでいる現在、電子書籍で本は読めるし、見てみたい建築はPCを開けば瞬時に出てくるし、保存も簡単であり、保管場所を考えず処分する必要もないのである。デジタル化の必要性を認識しながらも、紙書籍の表紙・タイトルの文字を見て、ほっとぬくもりを感じる自分がいるのである。
過去を振り返れるアナログの部分は、まだまだ必要なのではと思えてならない。
芋煮会発祥の地・なかやま~引き継がれる伝統文化~(令和5年7月号)
先日、YouTubeのBSよしもと企画「となりマッチ」という番組で、ご当地自慢プレゼン【中山町VS山形市】の対戦模様が配信されました。吉本興業の住みます芸人・ソラシド(水口さん・本坊さん)が進行役となり、両市町の1.スポット、2.イベント、3.グルメを紹介し、別会場のスタジオで6名の審査員が勝敗の判定を下すという企画でした。
当町は、1.旧柏倉家住宅、2.元祖芋煮会inなかやま、3.北前いも煮(芋棒煮)を紹介し、スタジオでの試食タイムもあり、結果は4対2で見事勝利となりました。勝敗には関係なく特に嬉しかったのは、北前いも煮について、魚醤だしが田舎っぽく優しい味、棒鱈が美味しい等と好評だったこと、そして、紅花が咲き誇った風景の旧柏倉家住宅を評価していただいたことです。
わが町にはまだまだ誇れる地域資源がたくさんあります。町内を見つめ直し町外にも自慢していけば、関係人口を新たに作り出すチャンスです。
「いも煮」というキーワードは、川でつながり、海でつながり、そして人々がつながって新しい交流が生まれ、未来へと引き継がれていくものです。
ぜひ、YouTube「となりマッチ」を検索してみてください。
郷土の誇りを未来に……(令和5年6月号)
田植えを終えた水面に美しい山々を映し出す季節となり、世の中も徐々にアフターコロナに向かって動き出しているようです。
日本へのインバウンドは増え始め、国内外旅行の交流人口、地域における関係人口も活気を取り戻しています。山形県内にも日本の伝統文化を体験できるコースを求めて来形する観光客が多くなっているようです。
そのような中、わが町では4月に八坂神社で大例祭が行われ、お神輿が練り歩き、お神楽も家々を回り、厄を祓ってくれました。5月3日には豊田の各地区・達磨寺・向新田地区の神社例大祭が行われました。豊田の5つの地区では、4年ぶりとなる子ども神輿の巡行やお神楽による厄払いが再開され、にぎやかな子どもたちの声が沿道に響き活気をもたらしていました。関係している大人からは声援や拍手が飛び、久々のにぎやかな雰囲気に、私も、清々しい朝に新たな夜明けを眺めるような気持ちが湧き上がってきました。伝統を守り続けている地域の方々に感謝です。
「郷土の誇りを未来につなぐ
人が輝く健幸のまち なかやま」
~思いやりの絆で築く
みんなの想いが響くまち~
土の記憶(令和5年5月号)
豊田山の桜も開花が早く満開となり初夏を感じるような4月中旬早朝、豊田小学校野草園で、ロータリークラブの皆さんにより鳥獣被害対策としての電気柵設置・草刈り等の整備が行われました。この野草園では、毎年11月に豊小の児童によって植栽されたヒメサユリが、5月下旬から6月にかけて可憐なうす紅色に咲きほこるのです。
園内には雑草が広がり、冬を越した球根から新芽が顔を出し始めていました。球根はイノシシなどの大好物でもあるため、多くを食べ荒らされた年もあり、春先の電気柵設置は欠かせないのです。また、雑草が生い茂っており機械で草刈りもしなければなりません。新芽を刈らないようにと目印の赤い棒を設置していきますが、雑草の中の新芽は隠れていてなかなか探せません。大昔の人だったらイノシシのように目を凝らし鼻を利かせ探し出せたのかもしれません。人間の持つ動物としての本能の退化なのでしょうか?
近年、ICT技術の目まぐるしい進歩により、AI(人工知能)が益々人間社会にとって便利な道具として普及してきており、チャットGPTが急速に広まろうとしています。教育現場への影響や情報流出、プライバシー侵害などへの懸念も高まりつつありますが、高い利便性で私たちの暮らしを大きく変える可能性があります。このような時代の流れの中で、私は、人間本来の本能が弱まっていくのではと心配です。AIをより良く活用するためには、五感を持った創造性のある人間が欠かせないのです。
豊田小学校野草園のヒメサユリ!子どもたちと共に守り続けていきたい大切な事業です。
つながり(令和5年4月号)
日本の3度目の優勝で幕が閉じられたWBCは、野球ファンのみならず多くの人々の記憶に残る大会となりました。栗山監督の「どうしてもグローバル化したい」という思いによる日系人ヌートバーの起用、打線のつながり、選手一人ひとりのつながりによるチーム力が大いに発揮されました。メンバー発表から一試合一試合をワクワクしながら応援観戦し、終わってみると、清々しい思いと《つながり》という言葉が心に残りました。
先日、町内の知人に勧められ、南陽市の夕鶴の里資料館に赴き、民話の語り部を鑑賞してきました。平成5年の開館から活動されている語り部の方からは、「鶴の恩返し」を主に「生活の中から生まれた民話とその心を未来へ語り伝える」という信念が感じられました。
中山町の宝である国の重要文化財旧柏倉家住宅で開催された「ひなまつり」も、町内外から多くの来客を迎え、過去・現在・未来へと継承されています。その一環として、中山昔語りの会の方々が、町にまつわる話や昔話を語り伝えてくれています。
民話は、「語る場」と「語る人」と「聞く人」という3つの要素があって成立すると言われます。昔話を聞き終えてWBC観戦の時の感動と似たような気持ちになったのは、スポーツと昔話という違った文化でも、人から人への《つながり》という相通ずるものを持っていと感じたからかもしれません。
わが町に伝わる民話も大切な宝です。ぜひ、皆さんも聞いてみてはいかがでしょうか。
【ふるさとの集い】3年ぶりの開催~故郷・古里・そして心のふるさと~(令和5年3月号)
去る2月19日3年ぶりに「東京中山会・ふるさとの集い」が東京日暮里にて満を持して開催されました。ウィズコロナでの開催ということもあり例年より少ない参加者となりましたが、石澤会長さんの「本当に開催して良かった」との温かい言葉のとおり、円卓を囲んで笑顔と笑い声が溢れ、「ふるさと・なかやま」を皆で合唱する会場には、柔らかな人を包み込むような空気が流れていました。会員メンバーは、中山町で生まれ育った方、父母の実家がある方の他に、その知人や近所付き合いで中山町には直接関係のない方もいらっしゃるのです。
「故郷」は生まれ育った土地、「古里」は一度住んだことがある、何らかの縁がある土地の意味もあるようです。東京生まれ東京育ちの人は、よく故郷がないと言いますが、「心のふるさと」は誰しもが持って良いものです。我が町をふるさとに選んでくださった方々が輪を囲み一緒に談笑している情景は何とも微笑ましく、まさしく中山町の応援団であると心強く感じました。
地元に住んでいる私たちには当たり前の景色・土の匂い・人の営みですが、それらを熱く大切に遠くから想ってくださっている方々がおられることに、改めて感銘を受けました。「東京中山会の皆さん」に感謝!!
「郷土の誇りを未来につなぐ ひとが輝く健幸のまち」に乾杯!!
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
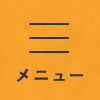
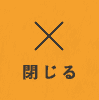

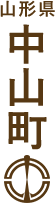




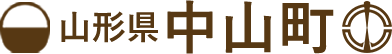
更新日:2023年12月15日