ひと・夢・まち 町長コラム(令和元年)
(広報なかやまより)
マネをしても、うまくいかないことを知っていますか?(令和元年12月号) 西郷どんの教え その8
「先ず我が国の本体を居え」が本文ですが、いつの時代も今よりもっと文明の進んだ豊かな国になりたいと思うのは当然のことと思います。
西郷さんが生きた明治は、特に、それまで鎖国政策により外国文化が断絶されていたものが急に開放されたということで、何でも新しいものに魅力を感じ、限りなくほしいと思った時代だったのです。文明開化は時代の要請であり、それが我が国発展の一番の近道であると国民も政府も考えるようになったようです。しかし、西郷さんは、長い目で見て悔いがあってはならない、まずは自分たちの足元からしっかりと見つめていくことを注意喚起していたのです。
今、地方創生が叫ばれて6年。今後の中山町を創造する時に、先ずは我がふるさと「中山町」を知ることから始め、その後、他の町づくりの長所を取り入れることが重要であると思っています。町民みんなで住み続けたい町を考えていきましょう。
楽なこと、上手にやることを考えていませんか?(令和元年11月号) (西郷どんの教えvol.6)
この教えの本文は、「作謀を用いず」です。
ことの大小にかかわらず、正しい道を真心をもって貫き通す。一事の策略を用いてはいけない。多くの人は困難なことに当たると一時逃れのごまかしをして避けて通るような策略を用いる。そしていったん通り過ぎると、あとは何とかなると考えるが、決してそういうものではない。ごまかしを通したわざわいが、必ず生じて失敗する結果になるものである。正しい道で行えば、その時は回り道のように思えるが、長い目で見れば必ず成功は早いものである。
地方創生が叫ばれて5年、少子高齢化・人口減少に歯止めはかからず、東京圏一極集中も是正されずにますます拍車がかかっている現在、交流人口・関係人口を増やすことはまちづくりの一考と言われています。
しかし、イベントのような一過性のものでは町を生き続けさせることはできない。西郷どんとの縁、日体大の集団行動を含む合宿誘致、柏倉家住宅を含む紅花文化の日本遺産認定、そして国の重要文化財指定等、人を引き付ける資源は多くある。本物を継承・発信できる施策を考えることがこれからの課題だと思います。
友達の長所を知ってますか?(令和元年10月号) (西郷どんの教えvol.5)
この教えの本文は、「人材の登用」についての教えです。
「学校やクラスの役割を決めるときは、その人、それぞれの良いところ、つまり長所を生かした決め方をしたほうが良い。皆をまとめることが得意な人や、一つのことをコツコツと粘り強くやれる人もいる。どちらが上でも下でもない。その長所を見つけ生かす決め方をするように心がけることが大切である」としています。
西郷さんは、小人とか君子とか細かく厳格に区別することは害があるといっています。それにこだわって無理やり区分し、人材を差別するのはおかしいと言っています。大古より世の中の十中七、八は普通の人であり、皆それぞれ長所を持っているので、その長所を採って適材適所の職につけその才能を発揮させるがよいと言っています。
人は何らかの役を与えられ生きているものだと思います。一人ではできないことでも皆が集まれば強い力となって未来を切り開けると私は確信しています。
「ありがとう」って 言われるくらい やっていますか?(令和元年9月号) (西郷どんの教えvol.4)
この教えの本文は、「万民の上に立つ者は」を問うている一文です。
国民の上に立って政治を行う者は、先ず以って己を常に省みて、自分の行いを正しくし贅沢や奢りに流されず、節約をして無駄を省き仕事を立派に果たさなければならない。そして人民の模範となって、・・・・と、記されています。
これを小・中学生向けに言い換えると、「学校やクラスで係の仕事を持つ人は、いつも友達への思いやりを持ち、正しい行いをし、勉強をがんばって、他の友達の手本となるように進んで行動することが大切だよ。そして、そんな君を見ている他の友達が、『いつも僕たち、私たちのために進んで動いてくれてありがとう』と思われるくらいでなければ、学校やクラスはまとまらないものだよ」と教えています。
改めて我が身を振り返ると、まだまだ未熟です。
先日、駅前の広場(道路)で、近所の幼児とキャッチボールをしていたところ、私が後逸してしまい、ボールは止まっていた自動車に当たりお叱りを受けました。いくら子供用のボールとは言え、不注意ではなく、この教えのごとく私の倫理観の問題であると深く反省しました。(申し訳ございませんでした。)
改めてこの教えを心に刻み皆さんと共に歩んで参りたいと思っています。
「知・徳・体とは?」(令和元年8月号) (西郷どんの教えvol.3)
三章の原文は「政の大体は文を興し、武を振い、農を励ますの三つにあり。」と、政治の根本は、学問を興し、軍備を充実し、農業を奨励することを教えています。国づくり、町づくりの基本は教育、わが身を護る防災、そして第一次産業である農業の振興であり、その他の全てのことは、皆この三つの課題を実現させるための手段であり、この三つの課題を後回しにして、他のことを先にするようなことは決してあってはならない。と、言っています。
この三つを学校での大切なことに言い換えれば、よく学び「知」、よく運動し体を鍛え「体」、そして、学校のため人のために思いやりの心を持つ「徳」を重んじることになるようです。町づくりの観点から言えば「文化」「健康」「共助」となります。時代は変われど、この教えは心に響いてきます。
今年成人式を迎えられた若人にとっても、我々人生百年時代を生き抜く者にとっても、常に一考すべきことである。と思います。
「決めたことに後から文句を言っていませんか?」(令和元年7月号) (西郷どんの教えvol.2)
サクランボの季節も終わり、わが町特産のスモモの季節になりました。
令和の時代が幕を開け2か月が過ぎ、学生の皆さんにとっては夏休みが間近で、楽しい気持ちでいっぱいでしょうか。この1学期は昨年度の反省を踏まえて、これからの1年の目標を立てた時期ではなかったでしょうか。個人の目標もあれば、クラスの目標、学校の目標を掲げられたのではないでしょうか。町でも「住み続けたい中山の未来づくり」のために、「健幸まちづくり」を推進しています。「町民の町民による町民のためのまちづくり」です。
時代が違えども、西郷さんが生きた時代も学校やクラスで決めた目標やルールなどは守らなければならなかったようです。皆で決めたことが、今日はできないとしたら、学校やクラスをまとめるどころか、みんなの考えが一つになっていない証拠だよ。と、教育されていました。
「決めたことは守る。それが学校やクラスが一つになるということ」
「自分のことを後回しにできますか?」(令和元年6月号) (西郷どんの教えvol.1)
社会の中でもそうですが、学校やクラスの中でも一人一人が何らかの係や役割、仕事を持っていると思います。地域では「隣組長」は何年かに1回は必ず回ってきます。そして地域のため、クラスのためにどんな仕事であっても、全力で取り組み、また自分勝手な行動をしてはいけないということです。「利己主義」と「利他主義」という言葉がありますが、「利他主義」を重んじる方は、他人の幸福や利益を図ることをまず第一に考えます。
西郷さんも明治維新の時は自分が最も大切にしていた「敬天愛人」の精神に基づき仲間と共に国づくりを進めたのだと思います。みんなのためになることを第一に考え、そして、地域やクラスの誰がみても正しいという方法で進めていかなければならないのです。そして、「時として、もし、自分より優れた人が現れたら、すぐに交代するぐらいの大きな心を持たなければ、いい地域やクラスにはならない」と言っています。
「南洲翁遺訓」について(令和元年5月号) (西郷どんの教えvol.0ゼロ)
昨年の6月から連載していました「西郷隆盛・十の訓え」が先月で終了しましたが、今月からは西郷一族と縁のある町として、もう少し「西郷隆盛」について学んでいきたいと思います。「西郷隆盛・十の訓え」の著者であり、一昨年来町された隆盛の曾孫である西郷隆文氏が、「南洲翁遺訓」についてわかりやすく青少年向けに書かれた「西郷どんの教え」という書を紹介していきます。
遺訓とは故人の残した教えのことですが、「南洲翁遺訓」は明治23年に発行されました。ただ、西郷さんの遺訓なのに、作った人は薩摩藩(鹿児島県)の人ではなく、庄内藩(山形県・鶴岡市)の人なのです。これには明治維新終焉の時に起こった「戊辰の役」での出来事が大きく関わっています。新政府軍と戦っていた庄藩は敗れ、厳しい罰があると覚悟していましたが、寛大な処置が下されます。このような「王道的な処置」に感銘を受けた庄内藩の人たちは、8年後に、指示を出した西郷隆盛を訪ね直接話を聞いたそうです。その時話したことを後にまとめたものが「南洲翁遺訓」です。
この書は、西郷さんを理解する上でも役立ちますが、皆さんのこれからの人生の中において、全てがその通りなどと思うことはないにしても、一つでも役に立つ言葉があれば幸いと思っています。47もの教えがありますので、これからの4年間、一緒にお付き合いください。
「天」に問え。(平成31年4月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.10)
先月、日米野球界が誇るプレーヤー・イチロー(鈴木一郎)が現役を引退しました。野球の世界で常に挑戦し続けた一人の人間が、静かにバットを納めたその瞬間、一つのことをやり遂げた姿があまりにも美しく、言葉に言い表せない時間でした。彼の行動は決して他人と比べることはなく、その結果に対しても自慢するなどという低次元のレベルでもなく、淡々と続けてきたことを当たり前のごとく話す姿が、何故か西郷隆盛とダブってしまいました。
「不可能」の反対語は「可能」ではない。「挑戦」だ。
米野球界全球団で「42」が永久欠番となっている米野球界初の黒人プレーヤー、ジャッキー・ロビンソンの言葉です。イチローも常に前向きに挑戦し続けたことを話していました。誰かに言われたわけでもなく、誰かの責任にするでもなく、「今、自分がやるべきことは何だろう」、「何が足りていないから、このような状態なのか」自問自答し、27年間野球の道を歩んできたのだと感じました。まさに西郷さんが言っていた「敬天愛人」そのものであり、天に問い、天を目指して命の炎を燃やしきった野球人生だったと思います。
西郷さんは、自らの正道は常に天命を果たすことであって、そのために、「天」を敬い、使命を受け入れることが、世の中や人を大切にする道につながると考えていました。
今後は、「敬天愛人」・「南洲翁遺訓」について考えていきます。
恥は堂々とかけばいい。(平成31年3月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.9)
人生というのは、「山あり谷あり」などとよく言われますが、谷底から山の頂を見ている時の方が多いような気がします。ただ、うまくいかない時に怖いのは、再び失敗するのではと恐れ、新たな挑戦ができなくなることです。正道を行う勇気がなくなってしまうことではないでしょうか。
西郷さんの人生もいつも順風満帆ではなかったようです。二度におよぶ島流しなど幾多の失敗を重ねながらも、自分を信じ、これから先の国の姿を想像しながら、先頭に立ってきました。「生き恥」をさらしながらも、生き残った我が身を振り返り、「自分だけが生き残ったのは、まだ果たすべき使命があるからなのだ」と、自問自答していたのです。
人生において、過去を変えることはできません。しかし、現実を受け入れて前に進むのなら、やり直しはいつだってできます。正道を貫くために、間違いや過ちを認めることは何の恥でもありません。間違っていることをごまかしたり、取り繕ったりする方が恥ずかしいことだと、西郷さんの『訓え』が気づかせてくれます。
失敗や過ちを恐れず、恥は堂々とかいて正道を行い続ける。前に進んだ分だけ、未来は充実しているはずです。
自分を大事にしすぎるな。全ての悪事はそこから生じる。(平成31年2月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.8)
町民の皆さんのおかげで、2期目を迎えることができました。巻頭ページで、町政への意気込みを書かせていただきましたが、決意を新たに、取り組んでまいりたいと考えています。この町長コラムもひと月だけ休載しましたが、今月号からまた再開しますので、よろしくお願いします。
さて、今回の訓えは「自己愛」の落とし穴についてです。
西郷さんは「自分を愛しすぎること、つまり自分さえよければ他者はどうでもいいような考え方は、最も慎むべきこと。修業がうまくいかないことも、事業が成功しないことも、過ちを改めることができないのも、自分の功績を誇り、おごり高ぶるのもすべて自分を大事にしすぎる気持ちから生ずることなのだから、決して利己主義に陥ってはいけない」と訓えています。
人は、確かに成果を求めます。認められたい、褒められたい。しかし、西郷さんはそういう考えとは逆に、「すぐ認められなくともよい。」と考えていましたし、また、もっと言うならば、そのようなことすら考えず生きていた方が西郷さんだったのではと私は感じます。
人のため、国のため、そして自分が信じた道のために、信念を持って生きた西郷隆盛だからこそ、今の日本の礎を築いた人物になったのだと思います。
NHK大河ドラマ「西郷どん」は終了しましたが、平成29年度から町が取り組んできました「西郷隆盛・従道兄弟と縁ある中山町」PR活動は、町の重要な歴史文化として大切に継続していかなければなりません。
西郷隆盛・十の「訓え」も今回を含めあと3回となりました。町民の皆さんの心に一つでも留めていただければ幸いです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
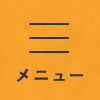
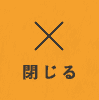

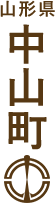




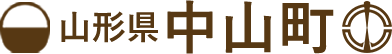
更新日:2023年09月01日