ひと・夢・まち 町長コラム(平成30年)
(広報なかやまより)
「当たり前」とは、不測の事態が起こること。(平成30年12月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.7)
今年も自然災害が日本各地に発生し、多くの方々が犠牲になりました。大雪被害から台風、地震、土砂災害など、予想・想定外の出来事に見舞われた地域の方々には心からお見舞いを申し上げます。
当町でもこうした不測の事態に備えて、このたび、最新の当町独自の防災ハザードマップを全戸に配付しました。不測の事態の中では、その時その場で瞬時に判断し、結論を出して実行に移さなければなりません。冷静に物事の道理を見極め、最善と思える判断をし、対処するための備えはどのようにすればいいのか? このたび作成した「わが家の防災:もしものときに備えて!」は、まさにその時に役立つようにとの思いで作られています。
災害は必ず発生します。日頃からその意識が大切なのです。
西郷さんが生まれ育った薩摩藩での郷中教育では、「もし、こうしたことが実際に起きたら、その時はどう行動すればいいのか」について毎日のように話し合っていたようです。子どものときから培ってきた精神のようなものです。先日、当町の中山中学校で、中学生が主体となっての防災訓練が行われました。昼夜間人口比が県内で最も低いわが町にとって、日中の防災に関して中学生が問題視したことはとても心強く思う反面、深刻な状況と再認識せざるを得ないと思わされました。
「災害は当たり前にやってくる」ということを意識し、不測の事態が起きたときは、動じない「胆力」と同時に、柔軟な「判断力」、素早い「決断力」、臨機応変な「対応力」を身につけることが必要です。これは、郷中教育で「日常の心得」と言われています。今の時代にも通じる納得の考え方です。
恩」は返せ。「恨み」は晴らせ。(平成30年11月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.6
似た言葉として、聖書の中に「目には目を、歯には歯を」という言葉があります。「やられたらやり返せ」というような意味で使ってしまいますが、まったく違う意味を持っていることを知っていますか?
西郷さんはいろいろな障害を抱えながらも、信念を持って国づくりをしていきました。恨まれたこともたくさんありましたし、恨んだこともきっとあったのではないかと想像してしまいます。しかし、西郷さんの行動には、憎しみや怒りにとらわれて復讐するということは無かったのです。戊辰戦争の有名な出来事の中で、庄内藩との戦い後の寛大な処置については今もって語り継がれています。西郷隆盛の「敬天愛人」の考え方を支持する人々は多く、庄内藩の重臣菅実秀によって「南洲翁遺訓」が世に出され、今も多くの人々に読まれています。
さて、「目には目を、歯には歯を」という言葉ですが、実は「目には目で、歯には歯で」が正しく、「目をつぶしてしまった罪には自らの目で償う」「歯を折ってしまった罪には歯で償う」という意味です。
また、「恨みは晴らせ」ですが、「晴らす」という字が示すように、どこか正々堂々とした清々しさがあり、正しい恨みの晴らし方には、生命が躍動するような前向きな勢いがあるのではないでしょうか。自分に打ち克つことで憎しみや怒りを乗り越え、成長の糧にしてより良い未来を築いていくことが大事なのだと教えてくれています。
理不尽は理不尽のままでよい。自分が理不尽なことをせねばよい(平成30年10月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.5)
生きているかぎり、誰もがさまざまな問題や困難に直面します。
幕末の日本も、現代社会に負けず劣らず理不尽に満ち溢れていたようです。西郷さんもその時代の波に巻き込まれ、幾度となく「死」を体感しています。主君の命で行動していた西郷さんは、主君斉彬公の死後、身内である薩摩藩からもそれまでの行動を否定され見放されてしまいます。
主君と共に国づくりの理想を掲げ進めてきたことを否定され、全てが信じられなくなった時、理解者であった月照と共に寒中の海に身投げします。西郷さんはかろうじて蘇生しますが、月照は助かることはありませんでした。西郷さんはこの事件により、薩摩藩から奄美大島への流罪がくだされます。藩が事実を隠ぺいし西郷さんを死んだことにし、偽名で島へ送られたのです。
しかし、西郷さんはすべてを受け入れるのです。
理不尽なことは沢山ありますが、決して復讐心にはとらわれなかったのです。
理不尽というのは、「自分にとっては、物事の筋道が通らない」とか、「道理に合わない」と感じていることです。であれば、自らの判断力が曖昧であれば、それだけ理不尽と感じるものが多くなります。逆に自分に克つということを大切にしていれば、事に向き合い、慎重に自らを振り返り、論語の「意なし、必なし、固なし、我なし」つまり、「私利私欲に走らない、無理強いをしない、固執しない、我を通さない」にあてはめると、真に理不尽なのは何か、が見えてくるそうです。そして、それに向き合うことが自らに与えられた正道なのだ、と言われています。
「理不尽なことをされたとしても、自分が理不尽なことを行わなければよい」
人生を歩む中、常に心に刻んでおきたい言葉です。そして、この言葉が、「敬天愛人」へ至る道へつながっていくのです。
「勇気」だけは、誰にも負けてはならない(平成30年9月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.4)
猛暑の夏休みの終わる日、夏の甲子園大会は、大阪桐蔭高校の2度目の春夏連覇で幕を閉じました。準優勝した東北代表の金足農業高校のはつらつプレーは、日本中に元気を与え、多くの可能性と夢を見せてくれました。暑い一日にもかかわらず、心は清々しく、若者の一球一打に感動したひと時でした。ありがとう!
現在はテレビという情報媒体があるので何処にいても感動を共有できますが、150年前の人々はその時々の状況を把握するのに、どれだけの時間を要したのか。そして、正確に伝わっていたのか、と思いを馳せてしまいます。いろいろな資料は残っているものの、定かではなく、同時に正反対のことが動いている可能性もあるようです。そのような時代に、熱い志を持った諸藩の志士たちが立ち上がり「維新」は成し遂げられ、明治という新しい時代が築かれました。
西郷どんが学んだ郷中教育の代表的な教えの一つに「泣こかい飛ぼかい、泣こよかひっ飛べ」という言葉があります。先輩が後輩に向かって、ここ一番、度胸が試される場面で使った掛け声だそうです。
「泣こうか飛ぼうか、泣くぐらいなら思い切って飛んでしまえ(迷うくらいなら、思い切って行動せよ)」
何かを成し遂げようとするときの「心意気」が伝わってきます。
一歩踏み出す「勇気」を持ち、信じることが大切なのです。
地元の出身者だけの金足農業高校のメンバーと応援する地元の人々の姿からは、「勇気」と「希望」が感じられ、地方創生を進めている今の日本にとって何が必要なのか、考えさせられた熱い夏の日でした。
「分をわきまえる」ほど、強くなる(平成30年8月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.3)
「分=立場」と読みかえれば、わかりやすい。
「自分の立場を考えて行動する」ということこそが、人生のさまざまな場面で迷ったとき、「損得でなく善悪で判断」し、「正道を行う」ための支えとなるとの訓えです。
人間の創造力は素晴らしく無限のものと信じていましたが、人間が中心に自然界が動くことは無く、私たちは自然界の一部であるということを常に思い知らされます。西日本豪雨での被災地の様子が連日メディアで流れ、普通の生活ができない状況を目の当たりにしたとき、人間そして都市というものは、なんて弱いものかと思い知らされるのです。
そして、連日のように復旧作業にあたられている方々に対して、改めて頭が下がる思いであり、「協働」の素晴らしさを感じ、常に町づくりの基本はここにあると思うのです。
自然の中に生きる。まちの中に生きる。そして人として生きる。分をわきまえて私たちは生きるのだと思うのです。
地位や名声に目がくらみ、「分をわきまえる」ことをおろそかにすると、思わぬことに足をすくわれかねません。
西郷隆盛という人は、出世欲や名誉欲に自分を見失うことなく、慎みを持って生きた人だったそうです。
「正道」を行い、それを楽しめ(平成30年7月号) (西郷隆盛・十の「訓(おし)え」vol.2)
いよいよ「なかやま健幸くらぶ」がスタートします。
・なんで今さら町中歩かんなねのや?
・いまも朝夕歩いてるよ!
・自分の身体は自分が一番知っている!
そのとおり!です。町民の皆さんは一人一人頑張っています。感謝です。
しかし、現在当町の高齢化(65歳以上)率は33%以上であり、7年後の2025年には約40%に達すると予想されています。平均寿命の延伸に伴い医療費の増加があげられ、町の負担が増加していきます。
このような中で、町民一人一人が健康を意識していただき、健康で幸せな暮らしを目指して健康寿命を延ばすことは大きな貢献につながります。加えて、歩きながら自分の町を見つめ直すことも必要なことであり、いろいろなことが見えてくると思います。
危険な道路・スペースなどもあるかもしれません。経済性を追求してきた我が国は、歩行者よりも自動車を優先してきたような気がします。確かに自動車は便利です。しかしその代償として人が行き交わさない町ができてきました。子供たちが安心して登下校、遊びに行ける町。まちに人があふれることを想像してみてください。
みんなの足で健幸なまちができれば素晴らしいと思います。
西郷隆盛さんは、常に「人として正しい生き方」を考え「正道」を行い貫き通した人だったそうです。そして大切なのは「心がけ」であり、「技術」や「技量」ではないということを言われていたそうです。正しい道を進み続ければ、次第にそれを楽しむ余裕さえ出てくるそうです。
一歩、家から出てみてはいかがでしょうか。その一歩が町をつくると思うのです。
迷ったときは「損得」ではなく「善悪」で判断せよ(平成30年6月号)
今年の1月から放送されている「西郷どん」。
昨年、鹿児島から当町に来ていただいた西郷隆盛さんの曾孫である西郷隆文さんが私に話してくれた言葉があります。それは隆文さんがお父さんから聞かされ続けた「西郷隆盛さんの言葉」で、実際に家訓のように言い伝えられている言葉ゆえに、とても重みのある響きが感じとれました。また、西郷家に語り継がれている「激動の時代の生き方」を記した10の「訓え」という本を知ったので、町民の皆様にもぜひ紹介したいと思います。これより半年、NHK大河ドラマを見ながら中山町と縁のある西郷家の訓えを覗いてみましょう。
一、迷ったときは「損得」でなく「善悪」で判断せよ
「地方創生」が叫ばれて5年が経とうとしています。人口減少問題、少子高齢化、人手不足への課題等々、地方は四苦八苦しています。そして、都心への一極集中は止まる所を知らない状況です。このような時代に地方が独自のまちづくりを考えようとしたとき、「町にとって何が得策なのか」は、当然検討していかなければなりません。しかし、最終判断をするときに「善いか悪いか」をないがしろにしたり、見極めることができない状況になったりした時には、安易な道となってしまう場合があります。
そこで、ちょっと一息!
西郷さんは常に本質を考えて行動していた人だったといいます。決して安易な道には進まず「正しい」と思った道を選択してきたのではないでしょうか。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(庶務担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
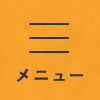
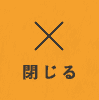

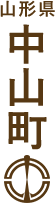




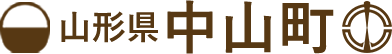
更新日:2023年09月01日